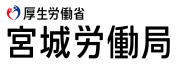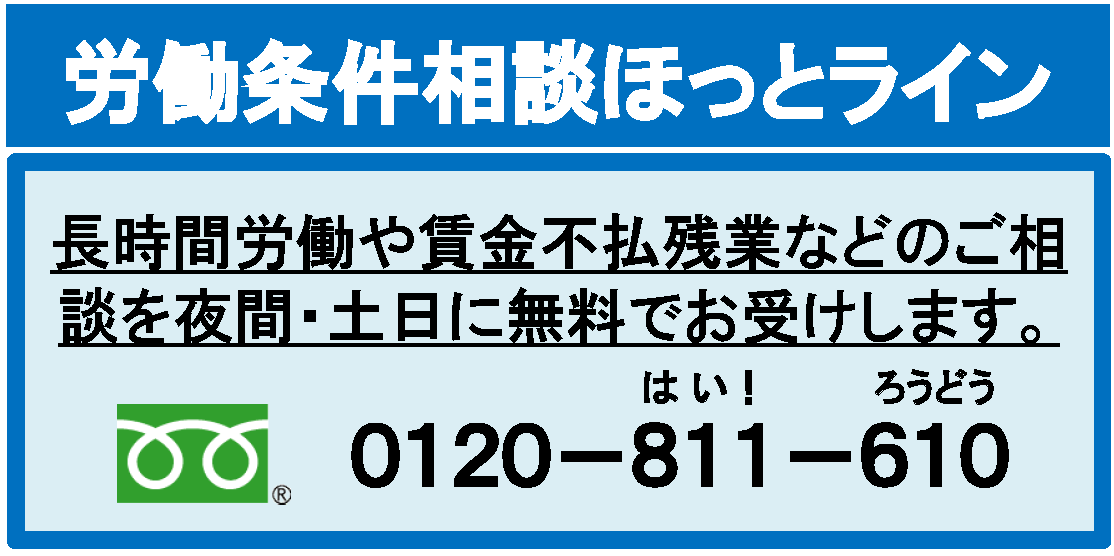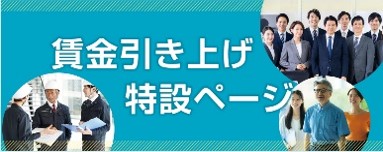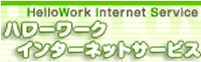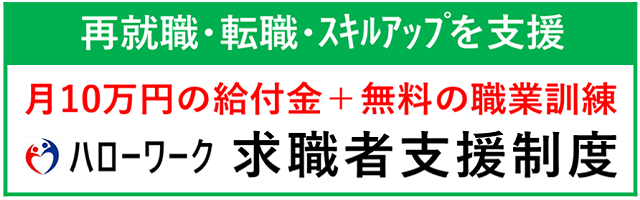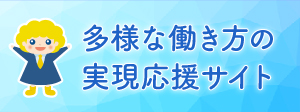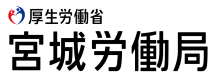- 宮城労働局 >
- 派遣労働者の受け入れルールの具体的内容(派遣先)
派遣労働者の受け入れルールの具体的内容(派遣先)
■派遣労働者の受け入れルールの概要
(1) 派遣社員を受け入れるときの主なポイント
(2) 平成30年労働者派遣法改正の概要
・「平成30年労働者派遣法の改正(派遣労働者の同一労働同一賃金)について」
(3) 「労働者派遣事業のQ&A」
(4) 「派遣先の皆さま向けのリーフレット」
・派遣先の皆さまへ・派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)
・派遣労働者を受け入れるために必要な対応があります!改めてご確認を
・派遣労働者の受け入れは派遣先にも責務が生じます
・派遣労働者の公正な待遇の確保、処遇の向上が求められています
■派遣労働者の受け入れルールの具体的内容
(★は平成27年改正事項、★★は平成30年改正事項)
(1) 期間制限
a.事業所単位・個人単位の期間制限(★)
・派遣就業とは、基本的には臨時的・一時的な働き方です・同一の派遣先事業所で派遣を受け入れることのできる期間は原則3年が限度です(派遣先事業所単位の
期間制限)。この限度を超えて派遣を受け入れるためには、過半数労働組合から意見を聞く手続きが
必要となります
・同一の派遣労働者の派遣を、派遣先の事業所の同一組織単位で受け入れできるのは3年が限度となります
(派遣労働者個人単位の期間制限)
・派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者の派遣を受け入れる場合など、期間制限の例外があります
・以前の「いわゆる26業務」への労働者派遣に期間制限を設けない仕組みは廃止されました
・要領第7の5・6
●「3年期間制限早わかり(Q&A)」
派遣可能期間を延長する場合の意見聴取の手続
派遣可能期間の抵触する日の通知例
延長後の派遣可能期間の制限に抵触する日の通知例
延長後の派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知例
派遣可能期間の延長についての意見聴取に対する意見の提出例
(2) 派遣元事業主との労働者派遣契約の締結
a.事前面接禁止
・派遣労働者を指名すること、派遣就業の開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止されて
います(紹介予定派遣の場合は例外)
・要領第7の16
b.適切な派遣契約の締結
・港湾・建設・警備・病院などにおける医療関係業務については派遣を受け入れることができません
・派遣契約を締結する前に、派遣元事業主に対して事業所単位の期間制限の抵触日(=期間制限違反となる
最初の日)の通知を行う必要があります(注:既に他の派遣元事業所から派遣労働者を受け入れたことが
ある場合は事業所単位の期間制限の期間の通算をする必要があるためです)
・派遣契約を締結する前に、派遣元事業主に対して、待遇情報等に関する情報提供が必要です。
(派遣先均等・均衡方式の場合)
派遣先事業主は、派遣先事業主に対して、比較対象労働者の待遇等の関する情報提供を労働者派遣契約締結
する前に提供を行う必要があります。
(労使協定方式の場合)
派遣先事業主は、派遣元事業主に対して、待遇に関する情報提供を労働者派遣契約締結する前に提供を行う
必要があります。
・派遣元事業主との間で締結する派遣契約においては、業務内容・就業場所・派遣期間などを定めるとともに、
派遣先の都合による派遣契約の中途解除の際に派遣労働者の雇用の安定を図るための措置についても定める
ことが必要です
・要領第5、第7の2
(3) 派遣労働者の適正な派遣就業
a.離職後1年以内の労働者の派遣受け入れ禁止
・自社で雇用していた労働者を、離職後1年以内に派遣元事業主を介して派遣労働者として受け入れすることは
できません
・要領第7の11
b.労働・社会保険の適用の促進
・受け入れる派遣労働者については、労働・社会保険の加入が適切に行われているかどうかを確認することが
必要です
・要領第7の14
c.苦情の処理
・派遣先は、派遣労働者からの苦情を適切に処理する必要があります
・要領第7の3(2)
d.派遣先責任者の選任・派遣先管理台帳の作成
・派遣先においては、各事業所において最低1人(さらに派遣労働者100人ごとに1人づつ追加)、派遣元事業所
との連絡調整や適正な派遣就業の確保を図るための「派遣先責任者」を選任する必要があります
・また物の製造の業務に派遣を受け入れる事業所等にあっては、これとは別に各事業所において最低1人
(さらに物の製造の業務に従事させる派遣労働者100人ごとに1人づつ追加)、「製造業務専門派先責任者」
を選任することとされています
・各責任者は、派遣先責任者講習を受講することが望ましいとされています
・派遣先は、派遣労働者の氏名や日々の派遣就業の始業・終業・休憩の実績などを記録する「派遣先管理台帳」
を事業所ごとに作成する必要があります
・要領第7の12・13
e.派遣労働者の雇い入れ努力義務(★)
・派遣労働者を受け入れていた組織単位において、派遣受入れ終了後に、同じ業務に従事させるために新たに
労働者を雇い入れようとする場合、一定の条件(※1)に合致する派遣労働者を雇い入れるよう努める必要が
あります
・要領第7の8・9
(※1)本人が継続して就業することを希望していること、派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一の業務について1 年以上継続して
派遣労働に従事した有期雇用派遣労働者であること、本人について派遣元事業主から直接雇用の依頼があること
f.労働者の募集情報の提供義務(★)
・一定の条件(※2)に合致する派遣労働者に対しては、派遣先において労働者(正社員に限らない)の募集が
あった場合はその募集情報を提供しなければなりません
・要領第7の8・9
(※2)派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一の業務について1 年以上継続して派遣労働に従事した有期雇用派遣労働者であること、
3年以上継続して労働に従事する見込みがある有期派遣労働者であること、本人について派遣元事業主から直接雇用の依頼があること
g.正社員の募集情報の提供義務(★)
・一定の条件(※3)に合致する派遣労働者に対しては、派遣先において正社員の募集があった場合はその
募集情報を提供しなければなりません
・要領第7の8・9
(※3)派遣先の同一事業所等において1 年以上継続して派遣労働に従事している有期又は無期雇用の派遣労働者であること
・つまり正社員の募集情報があれば、雇用期間や派遣元事業主の依頼の有無にかかわらず派遣先事業所内で1年
以上勤務している派遣労働者に対して広く周知する必要があるということです
対する労働者の賃金水準に関する情報の提供、派遣労働者に対する教育訓練や福利厚生施設の利用機会の
提供等の配慮を行う必要があります
・要領第7の4
(5)労働者派遣契約の中途解除
a.派遣契約中途解除の場合の新たな就業機会の確保(★)
・派遣契約を中途解約する場合、派遣先の関連会社での就業のあっせんなどにより派遣労働者の新たな
就業機会の確保を図ることが必要です
・要領第5の6(2)ハ
(6)労働契約申込みみなし制度
a.労働契約申込みみなし制度(★)
・派遣先が、期間制限を超えて労働者を受け入れた場合などの以下のような違法派遣があった場合は、
派遣先が本人に対して直接雇用する労働契約の申込みを行ったものと見なされ、派遣労働者が承諾した
段階で労働契約が成立します
・派遣禁止業務への派遣
・無許可事業主からの派遣
・期間制限を超えて労働者を受け入れた場合
・いわゆる偽装請負の場合
・要領第7の10

・一定の条件(※2)に合致する派遣労働者に対しては、派遣先において労働者(正社員に限らない)の募集が
あった場合はその募集情報を提供しなければなりません
・要領第7の8・9
(※2)派遣先の事業所等の組織単位ごとの同一の業務について1 年以上継続して派遣労働に従事した有期雇用派遣労働者であること、
3年以上継続して労働に従事する見込みがある有期派遣労働者であること、本人について派遣元事業主から直接雇用の依頼があること
g.正社員の募集情報の提供義務(★)
・一定の条件(※3)に合致する派遣労働者に対しては、派遣先において正社員の募集があった場合はその
募集情報を提供しなければなりません
・要領第7の8・9
(※3)派遣先の同一事業所等において1 年以上継続して派遣労働に従事している有期又は無期雇用の派遣労働者であること
・つまり正社員の募集情報があれば、雇用期間や派遣元事業主の依頼の有無にかかわらず派遣先事業所内で1年
以上勤務している派遣労働者に対して広く周知する必要があるということです
(4) 派遣労働者と派遣先社員等の均等・均衡待遇
a.派遣労働者と派遣先社員との均衡待遇の推進(★★)
・派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、派遣元事業主にa.派遣労働者と派遣先社員との均衡待遇の推進(★★)
対する労働者の賃金水準に関する情報の提供、派遣労働者に対する教育訓練や福利厚生施設の利用機会の
提供等の配慮を行う必要があります
・要領第7の4
(5)労働者派遣契約の中途解除
a.派遣契約中途解除の場合の新たな就業機会の確保(★)
・派遣契約を中途解約する場合、派遣先の関連会社での就業のあっせんなどにより派遣労働者の新たな
就業機会の確保を図ることが必要です
・要領第5の6(2)ハ
(6)労働契約申込みみなし制度
a.労働契約申込みみなし制度(★)
・派遣先が、期間制限を超えて労働者を受け入れた場合などの以下のような違法派遣があった場合は、
派遣先が本人に対して直接雇用する労働契約の申込みを行ったものと見なされ、派遣労働者が承諾した
段階で労働契約が成立します
・派遣禁止業務への派遣
・無許可事業主からの派遣
・期間制限を超えて労働者を受け入れた場合
・いわゆる偽装請負の場合
・要領第7の10