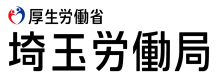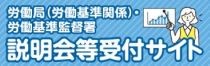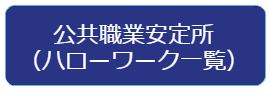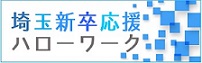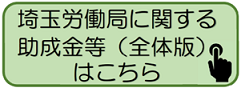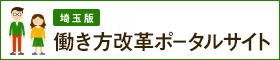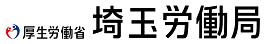- 埼玉労働局 >
- お役立ち情報 >
- 労働局からみなさまへ >
- ワークシェアリングを考えてみませんか >
- 新しい働き方調査報告書(概要版)
新しい働き方調査報告書(概要版)
1.調査の目的
本調査は、中小企業が99.2%を占める埼玉県における就業意識の状況、雇用形態に起因する問題、ワークシェアリングなどについて、県民や事業所を対象としてアンケート調査を行い、多様な働き方を適切に推進する上での基礎データを収集し、今後の労働行政施策に反映させようとするものである。
2.調査の概要
| 項 目 | 事業所調査 |
| 調査対象 | 埼玉県内の民間事業所 1,000事業所 |
| 抽出方法 | 平成14年事業所・企業統計調査による事業所名簿より抽出 (従業員規模別、地域別で配分。業種は「建築業」「製造業」「運輸・通信業」「卸売・小売業、飲食業」「金融・保険業」「サービス業」の6業種。) |
| 調査方法 | 郵送留置・訪問回収(回収の際に一部聞き取りも実施) |
| 調査時期 | 平成15年8月~10月 |
| 回 収 率 | 60.9%(回収数609件) |
事業所調査の結果概要
第1.回答者(事業所)の属性について
1.事業所の所在地
西部地域(34.6%)、東部地域(25.0%)、中央地域(24.3%)、北部地域(10.7%)、秩父地域(5.4%)。
2.業種
「製造業」(29.4%)が最多、「サービス業」(15.1%)、「小売業」(9.7%)、「建設業」(9.0%)の順。
| 建設業 | 製造業 | 運輸業 | 情報通信業 | 卸売業 | 小売業 | 飲食店 | 金融・保険業 | サービス業 | 不動産業 | 電気・ガス・ 水道業 |
その他 | 無回答 |
|
9.0 |
29.4 |
7.4 |
0.3 |
5.7 |
9.7 |
6.7 |
2.6 |
15.1 |
0.3 |
0.7 |
11.7 |
1.3 |
3.企業全体の従業員数
「10~29人」(20.0%)が最多、「100~299人」、「30~49人」、「100人以上」の順。100人未満が6割。

第2.多様な働き方・ワークシェアリングについて
1.ワークシェアリングの認知度
『内容を知っている』が6割弱。規模が大きい方が認知度が高い。
- 「内容を多少は知っている」(45.3%)が最多、「内容は知らないが、ことばはしっている」(27.9%)、「内容をよく知っている」(12.3%)、「内容もことばもい知らなかった」(8.7%)の順。
- 「内容をよく知っている」「内容を多少は知っている」を合計した『内容を知っている』は57.6%。
- 『内容を知っている』は、金融・保険業で7割台半ば、製造業で7割弱と高率である。また、規模が大きいほどその割合が高く、10人未満では約3割に過ぎないが、300人以上では8割を超えている。
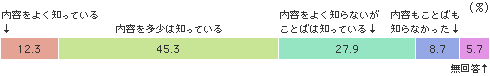
2.ワークシェアリングの導入・検討の状況
(1)ワークシェアリングの導入状況
ワークシェアリング導入率は約1割、類型別では「中高年対策型」が多い。業種別では運輸・情報通信業の導入率が高く、「中高年対策型」が中心。
- 「導入していない」(85.6%)が最多。導入しているのは、「雇用維持型(中高年対策型)」(4.9%)、「雇用維持型(緊急対応型)」(2.5%)、「多様就業型」(1.8%)、「雇用創出型」(0.2%)となっている。
- 重複回答を考慮して計算すると、ワークシェアリングが導入されている事業所は9.0%となる。
- 業種別で導入率が高いのは、運輸・情報通信業(17.0%)、サービス業(10.9%)。
- ワークシェアリングの類型別に導入が多い業種は、「雇用維持型(中高年対策型)」は運輸・情報通信業(10.6%)、卸売業(8.6%)、「雇用維持型(緊急対応型)」は飲食店(9.8%)。
(%)
| 導入していない | 「雇用維持型(中高年対策型)」 を導入している |
「雇用維持型(緊急対応型)」 を導入している |
「多様就業型」を 導入している |
「雇用創出型」を 導入している |
無回答 |
|
85.6 |
4.9 |
2.5 |
1.8 |
0.2 |
5.4 |
(2)ワークシェアリングの導入理由
「雇用維持型」「多様な働き方・場の提供」「人件費削減」「人材確保」が多い。
- 「従業員の雇用を守るため」(41.8%)が最多、「多様な働き方・場を提供するため」「人件費の削減のため」「有能な人材を確保するため」(ともに38.2%)の順。
(n=55, %)
| 従業員の雇用 を守るため |
多様な働き方・場を 提供するため |
人件費の削減 のため |
有能な人材を 確保するため |
企業として社会的な 責任を果たすため |
生産性の向上 のため |
他の雇用調整策 より実施しやすいため |
会社のイメージ アップのため |
労働組合(従業員) からの要請に応えるため |
その他 | 無回答 |
|
41.8 |
38.2 |
38.2 |
38.2 |
16.4 |
16.4 |
14.5 |
3.6 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
(3)ワークシェアリングを導入していない理由
「仕事の内容が導入に適さない」が最多で、規模が大きい方が割合が多い。
- 「仕事の内容が導入に適さない」(41.5%)が最多、「ワークシェアリングの内容や仕組み自体がよくわからない」(17.7%)、「賃金が減ることについて、従業員の了解が得られない(得られる見込みがない)」(16.7%)、「当事業所の規模では導入に適さない」(16.1%)の順。
(n=521, %)
| 仕事の内容が 導入に適さない |
ワークシェアリングの 内容や仕組み自体 がよくわからない |
賃金が減ることについて、従業員の 了解が得られない |
当事業所の規模 では導入に適さない |
世間に広く普及 していないので 時期尚早 |
生産性が低下する | 人事・労務管理 が複雑になる |
人件費の削減 効果が少ない |
従業員の質や 意欲が低下する |
他の雇用対策 を実施済み |
特に雇用対策を 実施する必要がない |
その他 | 無回答 |
|
41.5 |
17.7 |
16.7 |
16.1 |
13.2 |
12.3 |
11.5 |
9.2 |
9.2 |
2.1 |
11.7 |
5.0 |
3.5 |
(4)ワークシェアリングの検討状況
「今後も実施しない」が約5割、「今後検討したい」は約3割。「検討している」は1割以下。
- 「検討していないし、今後も検討するつもりはない」(49.5%)が最多、次いで「検討はしていないが、今後検討したい」(33.6%)、「雇用維持型(中高年対策型)について検討している」(3.3%)、「どのような型かは絞っていないが、検討している」(2.7%)の順。
- 「今後検討したい」は300~1000人未満で4割台半ばで最多、規模が小さい方が割合が少ない。
(n=521, %)
| 検討していないし、今後も検討するつもりもない | 検討していないが、今後検討したい | 「雇用維持型(中高年対策型)」について検討している | どのような型か絞っていないが、検討している | 「多様就業型」について検討している | 「雇用維持型(緊急対応型)」について検討している | 「雇用創出型」について検討している | その他 | 無回答 |
|
49.5 |
33.6 |
3.3 |
2.7 |
1.2 |
0.6 |
0.2 |
5.8 |
3.3 |
3.「多様就業型ワークシェアリング」を活用した多様な働き方の推進に対する考え
「どちらともいえない」が6割弱、『推進すべき』は2割台半ば。
- 「どちらともいえない」(57.6%)が最多、「どちらかといえば進めるべき」(17.9%)、「積極的に進めるべき」(6.6%)、「進めるべきではない」(3.0%)の順。
- 「積極的に進めるべき」及び「どちらかといえば進めるべき」を合計した『推進すべき』24.5%で「どちらともいえない 」の半分以下となっており、事業所の慎重姿勢がうかがえる。
- 『推進すべき』は、金融・保険業、卸売業では3割台半ば、運輸・通信業では約3割で、他業種よりも多く、飲食店では1割台半ばで少ない。規模ごとの差異はあまりない。
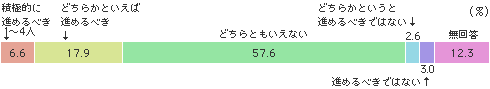
4.「多様就業型ワークシェアリング」を活用した多様な働き方のメリット
「従業員に時間のゆとり、仕事と家庭の両立」が最多、「女性・高齢者の雇用拡大」「人件費低下」の順。
- 「従業員に時間のゆとりができ、仕事と家庭の両立を図ることができる」(18.7%)が最多、「女性や高齢者などの働く場が広がる」(17.1%)、「人件費が低下する」(13.6%)、「雇用慣行や人事制度を変える機会になる」(11.2%)の順。また、「メリットは特にない」が26.6%を占める。
(%)
| 従業員に時間のゆとりができ、仕事と家庭の両立を図れる | 女性や高齢者などの働く場が広がる | 人件費が低下する | 雇用慣行や人事制度を変える機会になる | 有能な人材が確保できる | 中長期の雇用 の安定につながる |
生産性が向上する | 会社のイメージアップにつながる | 従業員の士気が向上する | 従業員能力開発が進む | その他 | メリットは 特にない |
無回答 |
|
18.7 |
17.1 |
13.6 |
11.2 |
10.8 |
6.9 |
6.4 |
5.6 |
4.6 |
4.6 |
3.4 |
26.6 |
16.4 |
5.「多様就業型ワークシェアリング」を活用した多様な働き方のデメリット
「職務の分担・引継、技能・技術の継承が難しい」、「人事・労務管理の複雑化」が多い。
- 「職務の分担・引継、技能や技術の継承が難しくなる」(31.2%)が最多、「人事・労務管理が複雑になる」(28.2%)、「生産性が低下する」「雇用が短期的、不安定になり、人材が定着しない」(ともに19.4%)、「会社への帰属意識や従業員の一体感が薄れる」(13.8%)の順。
(%)
| 職務の分担・引継、技能や技術の継承 が難しくなる |
人事・労務管理が複雑になる | 生産性が低下 | 雇用が短期的、不安定になり、 人材が定着しない |
会社への帰属意識 や従業員の一体感 が薄れる |
従業員の専門能力、技能が低下する | 質の高い人材を確保できない | 賃金などのコスト削減が進まない | その他 | デメリットは特にない | 無回答 |
|
31.2 |
28.2 |
19.4 |
19.4 |
13.8 |
11.0 |
10.7 |
9.4 |
3.8 |
10.3 |
16.1 |
6.「多様就業型ワークシェアリング」を活用した多様な働き方推進のために重要なこと
「導入企業への公的な優遇措置」「年金・保険制度改正」「従業員の技能低下防止・生産性向上」が多い。
- 導入した企業にとって負担増にならないよう、公的助成や税制等の優遇措置を講じること」(22.0%)が最多、次いで「年金や保険の制度を改正すること」(20.4%)、「従業員の技能の低下を防ぎ、生産性の向上を図ること」(19.4%)、「賃金や退職金、昇進・昇格などで公正に処遇すること」(17.7%)などとなっており、回答が分散している。
- 業種別では、建設業、製造業では、「導入企業への公的な優遇措置」、運輸・情報通信業、金融・保険業は「年金・保険制度の改正」、小売業、飲食店は「年齢・性別に関係なく仕事を選べるシステムづくり」、サービス業では「子育・介護をしやすい環境づくり」などが最多。
※ 回答の状況は、個人調査の第3の7の表に記載
7.勤労者の職業能力を高める方法で重視すること
「勤労者自らの自己啓発」が最多。
- 「勤労者が、自ら自己啓発すること」(52.9%)が最多、次いで「会社が、従業員の自己啓発を援助すること」(22.7%)、「会社が、従業員を教育訓練すること」(21.7%)の順。
(%)
| 自ら自己啓発すること | 会社が、従業員の自己啓発を援助すること | 会社が、従業員を教育訓練すること | 行政が、職業訓練サービスを提供すること | 行政が、勤労者について公的な認定・評価制度を整備すること | 行政が、教育訓練給付制度を整備すること | 会社が、社内資格制度を整備すること | 学校教育が、職業訓練・職業教育を提供すること |
民間企業が、職業訓練サービスを提供すること |
その他 | 無回答 |
|
52.9 |
22.7 |
21.7 |
18.6 |
16.6 |
15.8 |
11.3 |
7.2 |
2.5 |
4.8 |
20.4 |