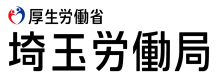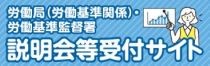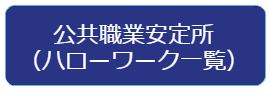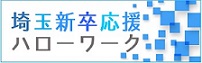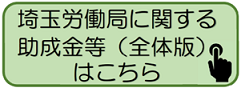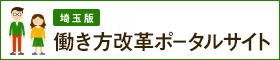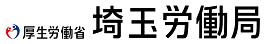- 埼玉労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職場におけるハラスメント防止対策 >
- 職場におけるハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置等
職場におけるハラスメント防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置等
職場におけるハラスメント(パワーハラスメント(パワハラ)/セクシュアルハラスメント(セクハラ)/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント(いわゆるマタハラ))を防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が厚生労働大臣の指針に定められています。
これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
職場におけるハラスメント対策パンフレット(厚生労働省ホームページ)
いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です。(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定です。)
改正法の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)。
パワーハラスメント(いじめ・嫌がらせ)に関するご相談は、お近くの総合労働相談コーナーへ
総合労働相談コーナー
セクハラ・いわゆるマタハラに関するご相談、企業のハラスメント防止対策についてのご相談は、
雇用環境・均等部指導課へ
電話 048-600-6269
これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。
職場におけるハラスメント対策パンフレット(厚生労働省ホームページ)
事業主が講ずべき措置
| (1) | 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 |
| ① ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発 ② 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発 |
|
| (2) | 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |
| ③ 相談窓口の設置と周知 ④ 相談に対する適切な対応 |
|
| (3) | 職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 |
| ⑤ 事実関係の迅速かつ正確な確認 ⑥ 被害者に対する適正な配慮の措置の実施 ⑦ 行為者に対する適正な措置の実施 ⑧ 再発防止措置の実施 |
|
| (4) | 併せて講ずべき措置 |
| ⑨ 当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知 ⑩ 相談、協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めと周知・啓発 |
|
| (5) | 職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置 |
| ⑪ 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置 |
事業主が行うことが望ましい取組
| (1)各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備 |
| (2)職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組 |
| (3)労働者や労働組合等の参画 |
| (4)事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組 |
| (5)他の事業主の雇用する労働者等からのパワハラや顧客等からの著しい迷惑行為 (いわゆるカスタマーハラスメント)に関し行うことが望ましい取組 |
令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について
改正法の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)。
| ハラスメント対策は、制度を作っただけで完成するものではありません。また、有効な対策は会社ごとに異なるものであり、法律の内容に沿って、会社の実情を踏まえて対策を充実させる努力をし続けましょう。 周知・啓発は、一度行えば良いというものではありません。
社内ネットワーク上に周知文書を掲載する例も見られますが、掲載されていることを労働者が知らないということであれば周知しているとは言えません。掲載や更新の都度、その旨をメール等で全労働者に周知することが必要です。 社内アンケート等で労働者の意識やハラスメントの実態を把握したり、社内の対策について意見を聞くことは、職場におけるハラスメントの未然防止や働きやすい職場環境の整備に役立ちます。 |
お問い合わせ先
総合労働相談コーナー
セクハラ・いわゆるマタハラに関するご相談、企業のハラスメント防止対策についてのご相談は、
雇用環境・均等部指導課へ
電話 048-600-6269