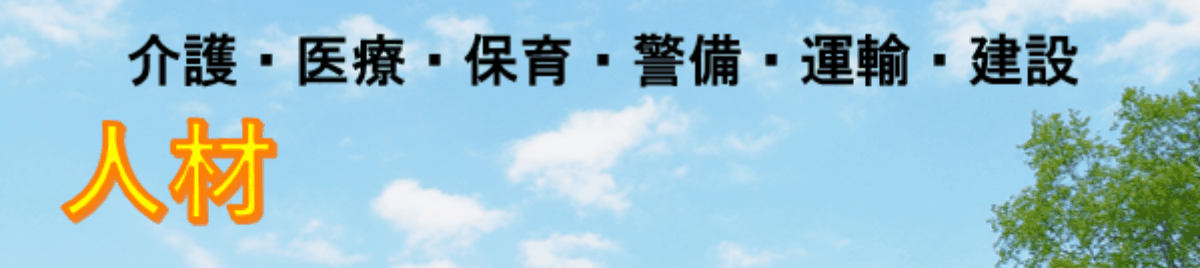よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)
Q1. 私は、正社員として10年勤務していますが、このたび家庭の事情で会社を辞めたいと思い退職願を提出しましたが、上司が受け取ってくれません。 会社が同意してくれないと私は退職できないのでしょうか?
A1.
民法では期間の定めのない雇用契約については、いつでも解約の申入れをすることができるとされており、解約の申入れの日から、2週間で終了することとなっていますので、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。
なお、会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されますので一度確認してみてください(就業規則で極端に長い退職申入れ期間を定めている場合などは、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合もあります。)。
Q2. 1年間の労働契約を結んでいますが、今回一身上の都合で、契約期間の半ばながらも退職したいと思っています。 会社からは引き留められていますが、どうしても勤めるわけにはいきません。 会社の了承無く辞めようと思っていますが、問題はないでしょうか。
A2.
雇用契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。
民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。
しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。
したがって、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害については、賠償を請求されることもあり得ます。
Q3-1. 労働者を解雇する場合の手続について教えて下さい。
A3-1.
労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告が必要となります。
また、予告が30日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要(これを「解雇予告手当」といいます。)となります。
(労働基準法第20条)
Q3-2. 労働者を解雇する場合の手続について教えて下さい。
A3-2.
労働基準法第20条の手続が適正であるからと言って、解雇が正当であるとは限りません。以下1.~8.に該当する場合、解雇は禁止されています。
以上のような労働基準法等で禁止されている条項に該当しない場合も、解雇を自由に行い得るというわけではありません。最終的には裁判所で判断する事になりますが、解雇が無効とされた次のような裁判例がありますので、参考にして下さい。
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解されるのが相当である。」
(最高裁第二小法廷昭和43年(オ)第499号昭和50年4月25日判決)
Q3-3. 3-2.の1.~8.の問題はないと思うのですが、会社の経営が非常に苦しく、これ以上雇用を維持するのは困難だと思い、労働者を解雇することにしました。経営が苦しければ、解雇は許されるのでしょうか?
A3-3.
ご質問のような整理解雇をする場合には、裁判例にて以下のような4要件が必要とされています。
Q4. 会社で総務を担当していますが、このたび労働者を就業規則の規定に基づき懲戒解雇にしようと思っています。 解雇予告は必要でしょうか?
A4.
会社の規則で定める懲戒解雇の事由に該当したとしても労働基準法に規定する解雇予告又は解雇予告手当の支払は必要となります。
ただし、その懲戒解雇の事由が事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為など労働者の責に帰すべき事由であった場合は、解雇予告又は解雇予告手当の支払は不要です。
なお、この場合は、労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。(労働基準法第20条)
Q5. 1年契約のパートタイム労働者を契約更新しながら雇用していますが、このような労働者に対して契約更新をしなかった場合、解雇の手続は必要ですか?
A5.
期間の定めのある労働契約の反復更新によって実質上期間の定めのない労働関係になったと認められる場合には、労働基準法第20条(解雇の予告)が適用されます。
しかしながら、同条が適用されない場合においても、事業主の更新拒絶により労働契約が突然終了することによって被る労働者の不利益を緩和することが望まし いことから、事業主は、1年を超えて引き続き労働者を使用するに至った場合は、当該労働契約を更新することなく期間の満了により終了させるときに、少なく とも30日前に予告を行うように努めて下さい。
Q6. 退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばよいですか。
A6.
退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)
Q7. 社内貯蓄及び私物のパソコンを残したまま、労働者が突然退職しました。 寮の部屋代の精算が済んでいないため、精算が済むまでこれらを返還しないでおこうと考えていますが、問題がありますか?
A7.
労働基準法第23条には、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと規定されています。
よって、労働者の社内貯蓄および同人のパソコンは、請求があれば7日以内に本人に返還する必要があります。(労働基準法第23条)
Q8. 資金繰りが厳しく手形の不渡りを発生させないために、取引先などへの支払を優先し、賃金の支払を待ってもらおうと考えていますが、問題ないですか。
A8.
賃金は一般の債権に優先される先取特権がありますので、賃金の支払の方を優先させなければなりません。
Q9. 私はある会社のパートタイマーとして20年勤務し、先日退職しました。 退職金の請求はできるでしょうか。
A9.
退職金については、法律上支払が義務付けされているものではなく、会社に退職金制度がある場合についてそれに従った支払が強制されているものです。
したがって、肝心なことは会社に退職金制度があるのかないのか、そこを確認することです。
制度があるにもかかわらず、それに従った支払をしないということであれば、労働基準法に抵触することになります。(労働基準法第24条)
Q10. 当社には、退職金規程がありますが昨今の景気の状況から、退職者に規程に基づく退職金の支払は困難となっています。 それでも、やはり全額支払わなければなりませんか。
A10.
退職金規程に基づき、所定支払日に全額支払う必要があります。(労働基準法第24条)
Q11. 私は会社を退職して4年になりますが、特に理由はありませんが今まで退職金について会社に請求をしませんでした。 これからでも会社に請求できますか。
A11.
会社に退職金制度があるのであれば、請求することは可能です。
ちなみに、毎月の定期賃金については3年、退職金については5年が時効となっています。(労基法第23条、労基法第115条)
Q12. 会社の経営が苦しいとのことで、賃金を引き下げると社長から言われました。 私としては納得がいかないのですが。
A12.
判例によれば、使用者が恣意的に労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは原則として許されるものではありませんが、就業規則の変更によるものについては、当該規則の条項が合理的なものである限り、個々の労働者の同意までは要しないとされています。
この場合、合理的なものかどうかは、
を総合勘案し判断すべきであるとされています。
また、使用者から予めまったく何の説明もなく、賃金支払日に一方的に賃金を差し引くことは、労働基準法第24条に抵触する可能性もあります。
なお大阪労働局では、法律違反とならない労働者個々の個別労働紛争に対して、労働局長の助言・指導やあっせんの場を提供する個別労働関係紛争解決制度を行政サービスとして提供しております。
Q13. 社長から突然賞与を減額すると言われました。 問題は無いのでしょうか?
A13.
「賞与」が、就業規則等により、予め支給時期、支給金額を定められているものであれば、賞与減額は労働条件の変更になり、原則として、個々の労働者の同意が無ければ、労働条件の変更は有効とされません。
ただし、労働者の同意を得ていないものの、就業規則の変更により労働条件の変更を行う際に、その変更条項が合理的である場合は、その適用を拒否することはできないとした判例があります。
なお、会社の業績により賞与支給金額を決定する、支給計算期間中の勤怠や業績評価等の査定等を経て賞与支給額を決定するなど就業規則等に定められている場合もあり、適正な査定等による減額であれば、問題はないと思われます。 労働基準法違反の可能性があり会社への監督・指導をお望みの場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署(所在地はこちら)に、
労働基準法違反の可能性があり会社への監督・指導をお望みの場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署(所在地はこちら)に、
 労働者と会社間の労働に関する民事上のトラブルについては各総合労働相談コーナー(所在地はこちら)へご相談下さい。
労働者と会社間の労働に関する民事上のトラブルについては各総合労働相談コーナー(所在地はこちら)へご相談下さい。
A1.
民法では期間の定めのない雇用契約については、いつでも解約の申入れをすることができるとされており、解約の申入れの日から、2週間で終了することとなっていますので、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。
なお、会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されますので一度確認してみてください(就業規則で極端に長い退職申入れ期間を定めている場合などは、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合もあります。)。
Q2. 1年間の労働契約を結んでいますが、今回一身上の都合で、契約期間の半ばながらも退職したいと思っています。 会社からは引き留められていますが、どうしても勤めるわけにはいきません。 会社の了承無く辞めようと思っていますが、問題はないでしょうか。
A2.
雇用契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。
民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。
しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。
したがって、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害については、賠償を請求されることもあり得ます。
Q3-1. 労働者を解雇する場合の手続について教えて下さい。
A3-1.
労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告が必要となります。
また、予告が30日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要(これを「解雇予告手当」といいます。)となります。
(労働基準法第20条)
Q3-2. 労働者を解雇する場合の手続について教えて下さい。
A3-2.
労働基準法第20条の手続が適正であるからと言って、解雇が正当であるとは限りません。以下1.~8.に該当する場合、解雇は禁止されています。
| 1. | 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間(労働基準法第19条) |
| 2. | 産前産後の休業期間及びその後30日間(労働基準法第19条) |
| 3. | 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条) |
| 4. | 労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇(労働基準法第104条) |
| 5. | 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働組合法第7条) |
| 6. | 女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8条) |
| 7. | 育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条) |
| 8. | 介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第16条) |
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解されるのが相当である。」
(最高裁第二小法廷昭和43年(オ)第499号昭和50年4月25日判決)
Q3-3. 3-2.の1.~8.の問題はないと思うのですが、会社の経営が非常に苦しく、これ以上雇用を維持するのは困難だと思い、労働者を解雇することにしました。経営が苦しければ、解雇は許されるのでしょうか?
A3-3.
ご質問のような整理解雇をする場合には、裁判例にて以下のような4要件が必要とされています。
| 1. | 人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性) |
| 2. | 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(配置転換などをする余地がないのか) |
| 3. | 解雇対象者の選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的であること) |
| 4. | 解雇手続の妥当性(労使の協議など) (東京高裁昭和51年(ネ)第1028号昭和54年10月29日判決等) |
Q4. 会社で総務を担当していますが、このたび労働者を就業規則の規定に基づき懲戒解雇にしようと思っています。 解雇予告は必要でしょうか?
A4.
会社の規則で定める懲戒解雇の事由に該当したとしても労働基準法に規定する解雇予告又は解雇予告手当の支払は必要となります。
ただし、その懲戒解雇の事由が事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為など労働者の責に帰すべき事由であった場合は、解雇予告又は解雇予告手当の支払は不要です。
なお、この場合は、労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。(労働基準法第20条)
Q5. 1年契約のパートタイム労働者を契約更新しながら雇用していますが、このような労働者に対して契約更新をしなかった場合、解雇の手続は必要ですか?
A5.
期間の定めのある労働契約の反復更新によって実質上期間の定めのない労働関係になったと認められる場合には、労働基準法第20条(解雇の予告)が適用されます。
しかしながら、同条が適用されない場合においても、事業主の更新拒絶により労働契約が突然終了することによって被る労働者の不利益を緩和することが望まし いことから、事業主は、1年を超えて引き続き労働者を使用するに至った場合は、当該労働契約を更新することなく期間の満了により終了させるときに、少なく とも30日前に予告を行うように努めて下さい。
Q6. 退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばよいですか。
A6.
退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)
Q7. 社内貯蓄及び私物のパソコンを残したまま、労働者が突然退職しました。 寮の部屋代の精算が済んでいないため、精算が済むまでこれらを返還しないでおこうと考えていますが、問題がありますか?
A7.
労働基準法第23条には、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないと規定されています。
よって、労働者の社内貯蓄および同人のパソコンは、請求があれば7日以内に本人に返還する必要があります。(労働基準法第23条)
Q8. 資金繰りが厳しく手形の不渡りを発生させないために、取引先などへの支払を優先し、賃金の支払を待ってもらおうと考えていますが、問題ないですか。
A8.
賃金は一般の債権に優先される先取特権がありますので、賃金の支払の方を優先させなければなりません。
Q9. 私はある会社のパートタイマーとして20年勤務し、先日退職しました。 退職金の請求はできるでしょうか。
A9.
退職金については、法律上支払が義務付けされているものではなく、会社に退職金制度がある場合についてそれに従った支払が強制されているものです。
したがって、肝心なことは会社に退職金制度があるのかないのか、そこを確認することです。
制度があるにもかかわらず、それに従った支払をしないということであれば、労働基準法に抵触することになります。(労働基準法第24条)
Q10. 当社には、退職金規程がありますが昨今の景気の状況から、退職者に規程に基づく退職金の支払は困難となっています。 それでも、やはり全額支払わなければなりませんか。
A10.
退職金規程に基づき、所定支払日に全額支払う必要があります。(労働基準法第24条)
Q11. 私は会社を退職して4年になりますが、特に理由はありませんが今まで退職金について会社に請求をしませんでした。 これからでも会社に請求できますか。
A11.
会社に退職金制度があるのであれば、請求することは可能です。
ちなみに、毎月の定期賃金については3年、退職金については5年が時効となっています。(労基法第23条、労基法第115条)
Q12. 会社の経営が苦しいとのことで、賃金を引き下げると社長から言われました。 私としては納得がいかないのですが。
A12.
判例によれば、使用者が恣意的に労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは原則として許されるものではありませんが、就業規則の変更によるものについては、当該規則の条項が合理的なものである限り、個々の労働者の同意までは要しないとされています。
この場合、合理的なものかどうかは、
| 1. | 就業規則変更によって労働者が被る不利益の程度 |
| 2. | 使用者側の変更の必要性の内容・程度 |
| 3. | 変更後の就業規則の内容の相当性 |
| 4. | 代替措置その他関連する他の労働条件の改善状況 |
| 5. | 従業員との交渉の経緯 |
| 6. | 同種事項に関する社会的一般的状況 |
を総合勘案し判断すべきであるとされています。
また、使用者から予めまったく何の説明もなく、賃金支払日に一方的に賃金を差し引くことは、労働基準法第24条に抵触する可能性もあります。
なお大阪労働局では、法律違反とならない労働者個々の個別労働紛争に対して、労働局長の助言・指導やあっせんの場を提供する個別労働関係紛争解決制度を行政サービスとして提供しております。
Q13. 社長から突然賞与を減額すると言われました。 問題は無いのでしょうか?
A13.
「賞与」が、就業規則等により、予め支給時期、支給金額を定められているものであれば、賞与減額は労働条件の変更になり、原則として、個々の労働者の同意が無ければ、労働条件の変更は有効とされません。
ただし、労働者の同意を得ていないものの、就業規則の変更により労働条件の変更を行う際に、その変更条項が合理的である場合は、その適用を拒否することはできないとした判例があります。
なお、会社の業績により賞与支給金額を決定する、支給計算期間中の勤怠や業績評価等の査定等を経て賞与支給額を決定するなど就業規則等に定められている場合もあり、適正な査定等による減額であれば、問題はないと思われます。
 労働基準法違反の可能性があり会社への監督・指導をお望みの場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署(所在地はこちら)に、
労働基準法違反の可能性があり会社への監督・指導をお望みの場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署(所在地はこちら)に、 労働者と会社間の労働に関する民事上のトラブルについては各総合労働相談コーナー(所在地はこちら)へご相談下さい。
労働者と会社間の労働に関する民事上のトラブルについては各総合労働相談コーナー(所在地はこちら)へご相談下さい。