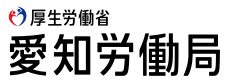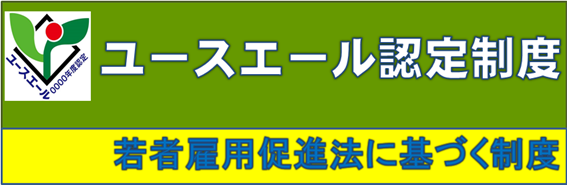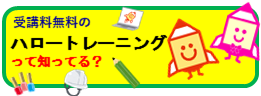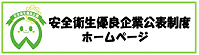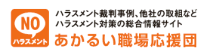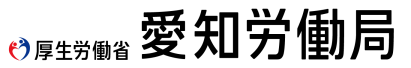- 愛知労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職業対策関係 >
- 法令・制度について >
- 障害者雇用について >
- 障害者を雇用する義務とは
障害者を雇用する義務とは
労働者を雇用する事業主は、民間企業であると官公庁であるとを問わず、身体障害者等に雇用の場を提供する社会連帯責任を有するということが、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法)という。)によって定められています。
「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。」(障害者雇用促進法第37条)
また、上記の法律に基づいて、一定の常用労働者を雇用する事業主に対し、「法定雇用率」以上の割合で障害者を雇用する義務が定められています。
「法定雇用率」は労働者(失業者を含む)に対する対象障害者である労働者(失業者を含む)の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされています。
○法定雇用率について
現行の一般の民間企業における法定雇用率2.5%、これは常用雇用労働者(*)である従業員40.0人に対し、そのうちの1人が障害者であるという割合になります。
*(1)常用雇用労働者の範囲
次の①~④のように1年以上継続して雇用される者(見込みを含みます。)をいいます。
※昼間学生や2つの事業主に雇用されている労働者、A型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の事業を実施する事業所をいう。以下同じ。)に雇用される労働者であっても、週所定労働時間が20時間以上である労働者は常用雇用労働者となります。
※外国人労働者(技能実習、特定技能を含む)についても常用雇用労働者に含まれます。
①雇用期間の定めのない労働者
②1年を超える雇用期間を定めて雇用されている者
③一定期間(1か月、6か月等)を定めて雇用される者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者、又は雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者(1年以下の期間を定めて雇用される場合であっても、更新の可能性がある限り、該当します。)
④日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されている者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者(上記③同様。)
※なお、「雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者」は、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するものをいいます。
(イ)雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されている場合。
ただし、更新回数等の上限が併せて明示されていることにより、1年を超えて雇用されないことが明らかな場合はこの限りではありません((ロ)に該当する実態にある場合を除きます。)
(ロ)雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新されない旨が明示されている場合又は更新の有無が明示されていない場合であって、類似する形態で雇用されている他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
また、以下の労働者については取扱いにご留意ください。
・「出向中」の労働者は、原則として、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主の労働者として取り扱います。なお、当該必要な主たる賃金を受ける事業主についての判断が困難な場合は、雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱って差し支えありません。
・「休業中」の労働者(育児休業等含む。)は、現実かつ具体的な労務の提供がなく、そのため給与の支払いを受けていない場合もありますが、事業主との労働契約関係は維持されているので、常用雇用労働者に含まれます。
・外国にある支社、支店、出張所等に勤務している労働者は、日本国内の事業所から派遣されている場合に限り、その事業主の雇用する労働者とします。したがって、現地で採用している労働者は含みません。
・生命保険会社の外務員等については、雇用保険の被保険者として取り扱われているかどうかによって判断してください。
・いわゆる登録型の派遣労働者の場合、契約期間に多少の日数の隔たりがあっても、同一の派遣元事業主と雇用契約を更新又は再契約して引き続き雇用されることが常態となっている場合には、常用雇用労働者に含まれる場合があります。具体的には次に掲げる基準を全て満たす場合は常用雇用労働者に含まれます。
①雇用されている期間が年間328日を超えていること。
②雇用契約の終了から次の雇用契約の締結までの間隔が、おおむね3日以下であること。
③雇用契約期間中に離職や解雇がないこと。
④1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
また、事業所と最初の雇用契約を締結した日から1年を経過していない派遣労働者であって、上記①~④の基準を満たし、かつ今後雇用契約期間が断続しないと見込まれることにより最初の雇用契約を締結した日から1年以上引き続き雇用されると見込まれる場合は常用雇用労働者に含まれる場合があります。
・65歳以上の労働者であっても、常用雇用労働者に含まれます。
(2)短時間労働者
短時間労働者とは、常用雇用労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(3)特定短時間労働者
特定短時間労働者とは、短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者をいいます。障害者雇用率の算定にあたり、分母である常用雇用労働者の範囲に特定短時間労働者は含まれませんが、分子である常用雇用障害者として、以下の「重度身体障害者」、「重度知的障害者」、「精神障害者」である特定短時間労働者がその範囲に含まれます(就労継続支援A型の利用者は除きます。)。
詳細は各ハローワークまでお問い合わせ下さい。
「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。」(障害者雇用促進法第37条)
また、上記の法律に基づいて、一定の常用労働者を雇用する事業主に対し、「法定雇用率」以上の割合で障害者を雇用する義務が定められています。
「法定雇用率」は労働者(失業者を含む)に対する対象障害者である労働者(失業者を含む)の割合を基準とし、少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定することとされています。
○法定雇用率について
| 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
| 一般の民間企業 | 2.5% (40.0人以上) | 2.7%(37.5人以上) |
| 特殊法人 | 2.8%(36.0人以上) | 3.0%(33.5人以上) |
| 国、地方公共団体 | 2.8%(36.0人以上) | 3.0%(33.5人以上) |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7%(37.5人以上) | 2.9%(34.5人以上) |
現行の一般の民間企業における法定雇用率2.5%、これは常用雇用労働者(*)である従業員40.0人に対し、そのうちの1人が障害者であるという割合になります。
*(1)常用雇用労働者の範囲
次の①~④のように1年以上継続して雇用される者(見込みを含みます。)をいいます。
※昼間学生や2つの事業主に雇用されている労働者、A型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10に規定する就労継続支援A型の事業を実施する事業所をいう。以下同じ。)に雇用される労働者であっても、週所定労働時間が20時間以上である労働者は常用雇用労働者となります。
※外国人労働者(技能実習、特定技能を含む)についても常用雇用労働者に含まれます。
①雇用期間の定めのない労働者
②1年を超える雇用期間を定めて雇用されている者
③一定期間(1か月、6か月等)を定めて雇用される者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者、又は雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者(1年以下の期間を定めて雇用される場合であっても、更新の可能性がある限り、該当します。)
④日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されている者であり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者(上記③同様。)
※なお、「雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者」は、次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するものをいいます。
(イ)雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されている場合。
ただし、更新回数等の上限が併せて明示されていることにより、1年を超えて雇用されないことが明らかな場合はこの限りではありません((ロ)に該当する実態にある場合を除きます。)
(ロ)雇用契約書、雇入れ通知書等において、その雇用が更新されない旨が明示されている場合又は更新の有無が明示されていない場合であって、類似する形態で雇用されている他の労働者が1年を超えて引き続き雇用されている等の更新の可能性がある実態にある場合
また、以下の労働者については取扱いにご留意ください。
・「出向中」の労働者は、原則として、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主の労働者として取り扱います。なお、当該必要な主たる賃金を受ける事業主についての判断が困難な場合は、雇用保険の取扱いを行っている事業主の労働者として取り扱って差し支えありません。
・「休業中」の労働者(育児休業等含む。)は、現実かつ具体的な労務の提供がなく、そのため給与の支払いを受けていない場合もありますが、事業主との労働契約関係は維持されているので、常用雇用労働者に含まれます。
・外国にある支社、支店、出張所等に勤務している労働者は、日本国内の事業所から派遣されている場合に限り、その事業主の雇用する労働者とします。したがって、現地で採用している労働者は含みません。
・生命保険会社の外務員等については、雇用保険の被保険者として取り扱われているかどうかによって判断してください。
・いわゆる登録型の派遣労働者の場合、契約期間に多少の日数の隔たりがあっても、同一の派遣元事業主と雇用契約を更新又は再契約して引き続き雇用されることが常態となっている場合には、常用雇用労働者に含まれる場合があります。具体的には次に掲げる基準を全て満たす場合は常用雇用労働者に含まれます。
①雇用されている期間が年間328日を超えていること。
②雇用契約の終了から次の雇用契約の締結までの間隔が、おおむね3日以下であること。
③雇用契約期間中に離職や解雇がないこと。
④1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
また、事業所と最初の雇用契約を締結した日から1年を経過していない派遣労働者であって、上記①~④の基準を満たし、かつ今後雇用契約期間が断続しないと見込まれることにより最初の雇用契約を締結した日から1年以上引き続き雇用されると見込まれる場合は常用雇用労働者に含まれる場合があります。
・65歳以上の労働者であっても、常用雇用労働者に含まれます。
(2)短時間労働者
短時間労働者とは、常用雇用労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
(3)特定短時間労働者
特定短時間労働者とは、短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者をいいます。障害者雇用率の算定にあたり、分母である常用雇用労働者の範囲に特定短時間労働者は含まれませんが、分子である常用雇用障害者として、以下の「重度身体障害者」、「重度知的障害者」、「精神障害者」である特定短時間労働者がその範囲に含まれます(就労継続支援A型の利用者は除きます。)。
詳細は各ハローワークまでお問い合わせ下さい。
| この記事に関するお問い合わせ先 職業安定部職業対策課 tel:052-219-5507 |