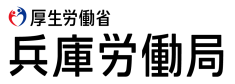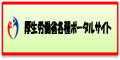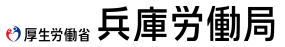- 兵庫労働局 >
- 誰もが働きやすい職場づくり
誰もが働きやすい職場づくり
安全で健康に働くことができる環境づくり
(1)長時間労働の抑制
① 長時間労働の抑制に向けた監督指導の強化等
長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による過労死等の労災請求が行われた事業場全数に対する監督指導を引き続き実施します。
また、11 月には「過労死等防止啓発月間」として長時間労働が疑われる事業場に対する重点監督を集中的に実施するとともに、「しわ寄せ防止キャンペーン月間」として大企業・親企業の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止に向けた周知啓発等の取組を行います。
過労死等防止対策(厚生労働省ホームページ)
しわ寄せ防止キャンペーン月間
② 中小企業・小規模事業者等に対する支援
生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者が抱える様々な課題に広く対応するため、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、労務管理の専門家による電話・メール・来所相談による個別相談支援、企業への訪問コンサルティング等の支援サービスの提供を行います。
全ての労働基準監督署に編成した「労働時間改善指導・援助チーム」のうち「労働時間相談・支援班」において、説明会の開催や中小規模の事業場への個別訪問により、改正労働基準法等の周知はもとより、時間外・休日労働協定の作成方法の教示等を中心としたきめ細やかな相談・支援を引き続き行います。
兵庫働き方改革推進支援センター
③ 令和6年度適用開始業務等への労働時間短縮に向けた支援
令和6年度適用開始業務等の建設業、自動車運転者、医師について、引き続き時間外労働の上限規制や見直し後の改善基準告示等の周知及び、特設サイト「はたらきかたススメ」による企業・国民等の更なる理解を促すため周知・広報に取り組むとともに、荷主等の取引先との取引条件改善などの環境整備を推進します。
医師については、兵庫県医療勤務環境改善支援センターと連携し、医療機関に対するきめ細やかな相談対応など、引き続き支援を行います。
トラック運転者については、引き続き、関係省庁とも連携しながら、「荷主特別対策チーム」において、発着荷主等に対して、長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないこと等についての要請と、その改善に向けた働きかけを行うとともに、賃金水準の向上に向けて、賃金の原資となる適正な運賃(標準的な運賃)を支払うことについて周知を行います。
はたらきかたススメ(外部サイト)
医療労務管理相談コーナー(外部サイト)
④ 過労死等防止対策の推進
過労死等防止対策推進法や「過労死等の防止のための対策に関する大綱」等に基づき、11 月の「過労死等防止啓発月間」の取組や、民間団体の活動に対する支援等の対策を効果的に推進します。
また、過労死等を発生させた事業場に対しては、企業本社における全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実施するとともに、一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対しては、企業の本社を管轄する都道府県労働局長から「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求め、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助言・指導(過労死等防止計画指導)を実施します。
(2)法定労働条件の確保・改善対策
監督指導、説明会等の各種行政手法を用い、基本的労働条件の枠組みの確立をはじめとする法定労働条件の確保に取り組むとともに、重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め厳正に対処します。
相談・投書等のほか、平日夜間、土日・祝日に実施している「労働条件相談ほっとライン」に寄せられた情報等、各種情報に基づき、法違反が疑われる事業場に対して、必要に応じて監督指導を実施するとともに、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知を徹底します。
労働基準・労働契約関係
(3)労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
① 兵庫第14次労働災害防止推進5か年計画の推進
労働災害による被災者を減らし、労働者一人ひとりが安全で健康に働くことができる職場環境の実現のため、令和5年度(2023年度)から、5年間にわたり、国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた「兵庫第14次労働災害防止推進5か年計画(以下「14次防」)」により労働災害防止対策を推進しています。
働く人の生命と健康はかけがえのないものであり、働くことで生命が脅かされたり、健康を損なうことは本来あってはならないものであることを踏まえ、「働く人の命を守る」ことを原点にして、減少目標を掲げて、労働災害の一層の削減に取り組みます。
特に、死亡災害、労働者の作業行動に起因する労働災害、高年齢労働者等の労働災害及び業種別の労働災害防止対策を推進するとともに、個人事業者等に対する安全衛生対策を重点に取り組みます。
14次防が掲げる減少目標は、死亡者数は、令和9年(2027年)までに令和4年(2022年)比で15%以上減少(27人以下)、死傷者数は、令和3年(2021年)までの増加傾向に歯止めをかけ、令和4年(2022年)と比較して令和9年(2027年)までに減少(5,129人以下)させることとしています。
兵庫第14 次労働災害防止推進5か年計画
②「兵庫リスク低減МS運動(2期)」の推進
14次防の目標達成に向けて、兵庫労働局の独自取組である「兵庫リスク低減MS運動(2期)」に、令和9年度まで継続して取り組みます。
MS運動※は、働く人の命を脅かすような重篤な災害の撲滅と、万一災害が起きても休業を要しない程度の軽微な被害に抑えられる安全・安心な職場環境の実現を目指して、経営トップが強い決意に基づき安全衛生方針を表明(取組宣言)し、職場の安全衛生に積極的に関わること、PDCA(P(計画)-D(実行)-C(評価)-A(改善))サイクルによる組織的安全衛生管理の運営を図ること、更にリスクアセスメントを継続的に実施し残されたリスク(残留リスク)を明確かつ重点的に管理することで、「許容できないリスクがない職場づくり」につなげるための運動です。
特に、中小企業にもMS運動の取組が浸透するよう、労働災害防止団体、関係業界団体並びに労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者及び発注者等、様々な立場の関係者と連携し、展開します。
※「MS運動」のMSとは、Management System(マネジメントシステム)の略語です。
兵庫リスク低減МS運動(2期)
③ 作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、職場における労働者の作業行動を起因とする労働災害(行動災害)が増加傾向にあります。特に中高年齢の女性をはじめとして発生率が高く、小売業や社会福祉施設を中心に増加しています。
このため、県内の主要な企業、地方公共団体、関係団体等を構成員とする「兵庫SAFE協議会(小売業)・兵庫 SAFE 協議会(介護施設)」を運営し、企業における自主的な安全衛生活動の導入を支援する等により、第三次産業で発生する「転倒災害」や腰痛等の「動作の反動・無理な動作」を防止し、管内全体の安全衛生に対する機運醸成を図ります。
第三次産業の労働災害防止
④ 高年齢労働者、外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
兵庫県では、働く高年齢者の増加(65 歳以上の雇用者数/過去 10 年間で 1.5 倍)に伴い、60 歳以上の労働者が労働災害で被災する割合は、5年連続して 25%(労働者4人に1人が高年齢労働者)以上となり、なかでも転倒災害の約半数は、高年齢労働者が占めています。このため、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向けた「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)の周知を図ります。
さらに、令和7年度からコースの新設が予定されている「中小企業による高年齢労働者の安全・健康確保措置を支援するための補助金(エイジフレンドリー補助金)」の普及促進を図ります。
外国人労働者を雇用する事業者に技能実習生をはじめとした外国人労働者が容易に理解できる労働安全衛生に関する視聴覚教材等(テキスト、VTR等)の活用を促進し、効果的な安全衛生教育の実施に向けた指導を行います。また、視覚的に示す安全表示等の活用を促進することにより、外国人労働者の労働災害防止対策を推進します。
また、兵庫労働局に設置する外国人労働者相談コーナー(2言語(ベトナム語、中国語))のほか、全国の労働局や労働基準監督署の相談コーナーとネットワークを構築した外国人労働者向け相談ダイヤル(13 言語)を活用し、引き続き丁寧な労働相談対応を行います。
転倒災害防止対策
高年齢労働者の安全衛生対策
外国人労働者を雇われている事業場の皆様へ
⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
令和7年4月から事業者が行う退避や危険箇所への立入禁止等の措置(労働安全衛生法第 20 条、第 21 条及び第 25 条に基づく措置)が、労働者以外の作業者にも拡大されるため、事業者に対して周知及び指導の徹底を図ります。
また、令和5年4月から施行されている危険有害作業を請け負わせる請負人(一人親方、個人事業者等)や同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対する健康障害防止に関する保護措置(労働安全衛生法第 22 条に基づく措置)に対しても、労働者と同等に措置を講じることが事業者に義務付けていることを、引き続き、周知し、指導の徹底を図ります。
併せて、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」について、周知・啓発を図ります。
個人事業者等の健康管理に関するガイドライン(厚生労働省ホームページ)
⑥ メンタルヘルス対策、産業保健活動の推進
長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、医師による面接指導や、ストレスチェック制度をはじめとするメンタルヘルス対策の取組が各事業場で適切に実施されるよう、あらゆる機会を捉え周知・指導を行うとともに、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」について広く周知を行います。
また、兵庫産業保健総合支援センター及びその地域窓口(地域産業保健センター)が行う、メンタルヘルス対策やストレスチェックの集団分析結果に基づく職場環境の改善などに係る助言・支援制度の利用勧奨を行うことにより、中小企業等の産業保健活動の促進を図るほか、団体経由産業保健活動推進助成金の周知を行います。
さらに、健康診断及び事後措置等の徹底を図るため、9月の「職場の健康診断実施強化月間」において、重点的に周知・指導を行います。
職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策関係
⑦ 新たな化学物質規制の周知、石綿ばく露防止対策の徹底
令和6年4月から、これまで法令の対象となっていなかった化学物質への対策の強化を目的として、労働者が有害な化学物質にさらされることのないよう、リスクアセスメント結果に基づき、事業者自らが自律的な管理を行うべく、全業種を対象とした改正法令が全面施行となっています。
この化学物質規制の措置について、令和7年2月に創設された「化学物質管理強調月間」(毎年2月)をはじめとするあらゆる機会を通じて周知を図り、丁寧な指導を行います。
また、改正石綿障害予防規則に基づく措置の徹底を図るため、石綿事前調査結果報告システムによる事前調査結果等の報告、建築物石綿含有建材調査者講習等の修了者による調査(*)の徹底など、石綿除去等作業時におけるばく露防止措置の周知・指導を行います。
*令和5年10月1日建築物、船舶(鋼製のものに限る)について施行、令和8年1月1日工作物について施行。
職場における化学物質対策
石綿ばく露防止対策
⑧ 治療をしながら仕事ができる環境の整備(治療と仕事の両立支援)
兵庫労働局では、病気を抱える労働者が治療をしながら仕事ができる環境を整備するため、県内の地方自治体、医療機関、関係団体等を構成員とする「兵庫県地域両立支援推進チーム」を設置し、多方面から関係者のサポートを行っています。
現在、推進チームにおいては、アクションプラン(5か年計画)に基づき、推進チーム内にワーキンググループとして、3つの作業部会(好事例集作成部会、イベント・セミナー作業部会、相談支援機関分科会)を設置・運営し、地域における両立支援に係る取組を計画的に推進しています。
また、主治医、企業・産業医と労働者(患者)に寄り添う両立支援コーディネーターのトライアングルサポート体制を推進するため、推進チームの取組を通じて、治療と仕事の両立支援カードを含めた「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を周知し、地域の関係者に対して、両立支援についての理解の普及を図ることとしています。
治療と仕事の両立支援について
(4)総合的なハラスメント対策の推進
① 職場におけるハラスメント防止措置の履行確保
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し、行政指導を確実に実施して法の履行確保を図るとともに、ハラスメント被害を受けた労働者からの相談に丁寧に対応し、紛争解決援助の実施等により迅速な紛争解決を図ります。
また、適切なハラスメント防止措置が講じられるように、事業主に対して、厚生労働省で委託する事業主・ハラスメント相談窓口担当者等向け研修やウェブサイト「あかるい職場応援団」の各種ツールの周知を行います。
労働施策総合推進法(パワーハラスメント関係)、ハラスメント総合対策関係
② 就活生等に対するハラスメント・カスタマーハラスメント対策の推進
カスタマーハラスメントの防止対策を推進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアル等を活用して、企業の取組を促します。
また、就職活動中の学生等に対するハラスメントについて、事業主に対して、ハラスメント防止指針に基づく「望ましい取組」の周知徹底を図り、自主的な取組を促します。
学生に対しては、大学への出前講座等の機会に、相談先等を記載したリーフレットを活用し、学生が一人で悩むことがないよう支援しつつ、学生からの相談等により事案を把握した場合は、事業主に対して適切な対応を求めます。
職場におけるハラスメントの防止のために(厚生労働省ホームページ)
過労死等事案をはじめとする労災請求事案に係る迅速・公正な処理
令和5年度は、過重な業務が原因で発症した脳・心臓疾患に係る労災請求件数、業務によるストレスなどが原因で発症した精神障害に係る労災請求件数のいずれも増加しています。
局内の関係部署と引き続き連携をしながら、迅速・公正な事務処理を一層推進します。
労災保険について
フリーランスの就業環境の整備
令和6年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」について、フリーランス(特定受託事業者)や委託事業者等に対し、あらゆる機会を捉え、同法の内容について周知啓発を行うとともに、フリーランスから本法の就業環境の整備違反に関する申出があった場合には、速やかに申出内容を聴取し、委託事業者に対する調査、是正指導等を行うなど、本法の着実な履行確保を図ります。
また、フリーランスや委託事業者等からの本法に関する問合せに適切に対応し、フリーランスから委託事業者等との取引上のトラブルについての相談があった際には、相談内容に基づき、必要に応じて委託事業者等への調査や「フリーランス・トラブル110番」への案内を行います。
さらに、全国の労働基準監督署に設置した「労働者性に疑義がある方の労働基準法相談窓口」に相談があった場合には、労働者性の判断基準を丁寧に説明するなど適切に対応し、申告がなされた場合には、原則として労働者性の有無を判断し、働き方の実態から労働基準法上の労働者に該当すると判断した場合は、各労働関係法令に基づき必要な対応を行うとともに、被用者保険の更なる適用促進を図るため、日本年金機構年金事務所及び労働局労働保険適用徴収部門への情報提供を徹底します。
テレワーク・フリーランス
多様な働き方の実現に向けた環境整備
適切な労務管理の下で安心して働くことができるよう、また、労働者個々のニーズに基づいて多様な働き方を選択し、活躍できる環境を整備するため、多様な正社員制度、選択的週休3日制等柔軟な働き方等について周知するとともに、勤務間インターバル制度等の導入を促進することにより、ワーク・ライフ・バランスの実現を推進します。
勤務間インターバル制度等について、「働き方・休み方改善ポータルサイト」を活用し、実例に即した説明を行う、「働き方改革推進支援助成金」を活用して、時間外労働の削減等に取り組む中小企業等への制度の導入促進を図ります。
年次有給休暇の取得促進に向けて、年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底、計画的付与制度及び時間単位年休の導入促進を行うとともに、例年10月に実施する「年次有給休暇取得促進期間」の集中的な広報に取り組みます。
さらに、病気休暇、ボランティア休暇等特別休暇についても、企業への導入支援を図ります。
働き方・休み方改善ポータルサイト(外部サイト)
障害者・高年齢者の活躍に向けた雇用指導・支援
(1)障害者の雇用率達成に向けた雇用指導・支援
全ての企業において法定雇用率が達成されるよう、全未達成企業に対して事業所訪問を中心とした複数回のアプローチを行い、障害者雇用につながるよう支援・指導を行います。
令和7年4月からの除外率10ポイント引き下げの該当業種の企業に対して周知を行い、令和8年7月からの法定雇用率の引上げ(民間企業2.5%→ 2.7%等)により新規に対象となる企業や、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している雇用ゼロ企業(障害者を一人も雇用していない企業)については、ハローワークが中心となって各種支援機関と連携し、職場環境の整備から求職開拓、定着の支援など企業ニーズに合った企業向けチーム支援を行います。
「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を開催し、職場の同僚に障害特性を正しく理解していただくことで職場定着につなげます。
中小事業主全体で障害者雇用の取組みが進展するよう、障害者の雇用の促進や安定に関する取組みなどが優良な中小事業主を認定する制度「もにす認定制度」(※)の周知及び申請勧奨等に取り組みます。
※企業と障害者が、明るい未来や社会の実現に向けて、「ともにすすむ」という思いをこめて、愛称を「もにす」と名付けました。
障害者雇用対策について
(2)高年齢者の定年延長・雇用継続の促進等
働く意欲と能力がある限り、年齢にかかわりなく活躍し続けることができる社会の実現に向けて、高年齢者雇用安定法により定められている65歳までの雇用を確保する措置(高年齢者雇用確保措置)に加えて、令和3年4月から努力義務とされている70歳までの就業機会を確保する措置(高年齢者就業確保措置)の導入に向けた、企業への制度周知・啓発指導を行います。
高年齢者雇用対策について