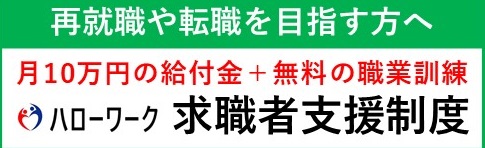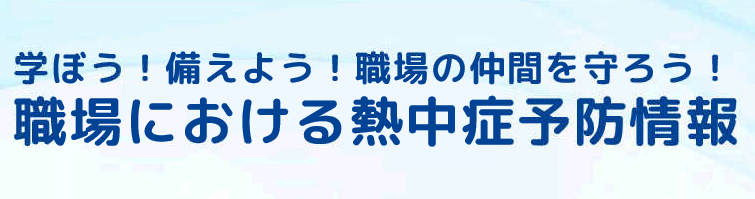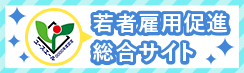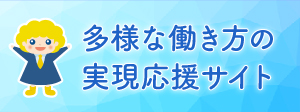- 青森労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用均等関係 >
- 法令・制度 >
- 職業生活と家庭生活との両立のために >
- 育児と仕事の両立を実現するために - 企業・管理職の方へ
育児と仕事の両立を実現するために - 企業・管理職の方へ
こちらのページでは、企業・管理職の方へ向けた情報を掲載しています。
従業員の方向けの情報をご覧になりたい場合は、下記リンクからご覧ください。
育児と仕事の両立を実現するために - 従業員の方へ(青森労働局ホームページ)
「母性健康管理措置」とは、男女雇用機会均等法に基づき妊娠中や出産後1年以内の女性労働者が保健指導や健康診査の際に医師や助産師から指導を受けた場合、その指導事項を守ることができるようにするために事業主が講じる義務がある必要な措置のことです。
具体的には以下のような措置が含まれます。
- 保健指導・健康診査のための時間確保
- 指導事項を守るための措置
- 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
なお、労働基準法においても母性保護の観点から以下の措置が定められています。
- 産前産後休業
- 妊婦の軽易業務への転換
- 妊産婦の危険有害業務の就業制限
- 妊産婦の変形労働時間制の適用制限
- 育児時間
より詳しく知りたい方は女性労働者の母性健康管理等について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
- 育児休業等の措置
- 個別の意向徴収・配慮(令和7年10月~)
- 介護離職防止のための早期の情報提供
- 雇用環境の整備
- 柔軟な働き方を実現するための措置等(令和7年10月~)
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置
- 労働者の配置に関する配慮
- 育児休業取得状況の公表
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
1歳未満の子を育てる労働者は、男性でも女性でも申し出ることにより育児休業を取得することができます。
また、産後休業を取得していない場合は、1歳までの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得することができます。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
両親ともに育児休業をする場合で、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2ヶ月になるまでの間で1年間、育児休業を取得することができます。ただし、育児休業の期間は親1人につき1年間が限度です。
出産した女性労働者の場合、出産日以後の産前・産後休業期間は、この「1年間」に含まれます。
ただし、育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日の翌日以降である場合、及び本人の育児休業予定日が、配偶者の育児休業の初日前である場合には、この限りではありません。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
産後休業をしていない労働者が、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで分割して2回、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。(育児休業とは別に取得可能)
育児休業とは違い、希望する場合は休業期間中に労使の合意に基づき一定範囲内で就業することも可能です。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
小学校3年生修了までの子どもを育てる従業員は、事業主に申し出ることにより、子どもが1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は10日まで、子どものための看護等休暇(子の看護等休暇)を1日又は時間単位で取ることができます。
①怪我をしたり病気にかかった子どもの世話をするときや、②予防接種や健康診断を受けさせるときのほか、③感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話をするとき、④入園(入学)式、卒園式に出席するときに利用できます。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
事業主は3歳未満の子どもを育てる労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮する制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。所定労働時間とは、就業規則等で定められた勤務時間のことです。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
- 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、以下5つの選択肢の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
- 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
- 事業主が講ずる措置を選択する際、労働者の過半数で構成される労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
- 短時間勤務制度
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
小学校就学の始期に達するための子を養育するため労働者が請求した場合に、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため労働者が請求した場合に、事業主は1ヶ月につき24時間、1年につき150時間を超えて時間外労働(法定労働時間数を超える労働)をさせてはいけません。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため労働者が請求した場合に、事業主は午後10時から午前5時までにおいて労働をさせてはいけません。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されています。
より詳しく知りたい方は育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
「トライアル雇用」とは、妊娠、出産・育児を理由に仕事から離れた求職者等が再就職に不安がある場合に、常用雇用への移行を前提として、原則3ヶ月間、その企業で試行雇用(有期雇用)として働いてみる制度です。試行雇用(トライアル雇用)期間中は、仕事や企業について理解を深められます。
また、事業主側はトライアル雇用として対象労働者を原則3ヶ月間の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、月額最大4万円、最長3ヶ月の支給を受けることができます。(トライアル雇用助成金)
トライアル雇用助成金の詳細については、下記ページをご確認ください。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)(厚生労働省ホームページ)
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省ホームページ)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」は、母子家庭の母等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
詳細については、下記ページをご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)(厚生労働省ホームページ)
両立支援等助成金
「両立支援等助成金」は、仕事と家庭(育児・介護等)の両立支援に取り組む中小企業主を支援する助成金制度です。コースや申請方法については下記ページをご確認ください。
くるみん認定
「くるみん認定」とは、従業員の子育てをサポートする企業を厚生労働大臣が認定する制度です。この認定は次世代育成支援対策推進法に基づいています。
認定を受けた企業は、「子育てサポート企業」として自社の商品や広告、ウェブサイトなどに「くるみんマーク」を表示でき、企業イメージの向上につなげることができます。
くるみん認定を受けた青森県内企業の一覧についてはくるみん・プラチナくるみん認定企業について(青森労働局ホームページ)をご確認ください。