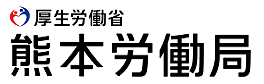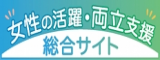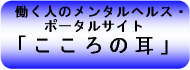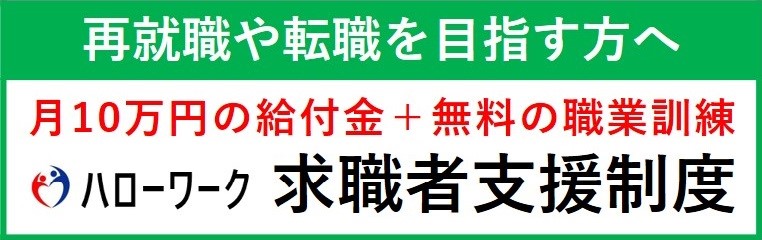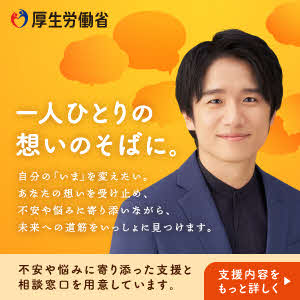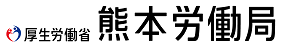- 熊本労働局 >
- ニュース&トピックス >
- くるみん認定通知書交付式を開催しました(医療法人 佐藤会 様)
くるみん認定通知書交付式を開催しました(医療法人 佐藤会 様)
| 医療法人 佐藤会 様 |  |
熊本労働局(局長 金成真一)は、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と家庭の両立支援の取組が優秀な法人として、医療法人 佐藤会をくるみん認定し、令和6年6月13日にくるみん認定交付式を開催しました。
医療法人 佐藤会 理事長 池田英世 様が出席され、労働局長から認定通知書を交付しました。
令和6年度第1号のくるみん認定となり県内32社目の認定企業(法人)となりました。

金成労働局長(右)から認定通知書の交付を受けられる池田理事長 様

左から高森人事企画室係長、池田理事長、金成労働局長
くるみん認定に係るインタビュー
A.(男性社員の感想)
私は、3人目の子どもが生まれたときに産後パパ育休を取りました。当時はコロナが流行していた時期で、感染のリスクを考えると、実家を頼ることは難しいと悩んでいたところでした。
そんなとき、勤務先の人事部から、「産後パパ育休制度」のお知らせがありました。私は今の部署に異動して1年も経っておらず、男が育休をとるという感覚がありませんでしたが、上司や同僚が後押ししてくれたこともあり、産後パパ育休を取得するになりました。
妻が産後入院している間は、上の子たちにご飯を食べさせ、保育園へ送り、掃除や洗濯をすませ、お風呂に入れ、寝かしつけてと、毎日バタバタでした。家に戻ってきた妻からは、「大変さがわかった?」と言われました。上の子が生まれたときは、里帰り出産でしばらく別々に暮らしていましたが、今回は生まれたばかりのわが子と触れ合う時間をとることができ、とても貴重な時間でした。
産後パパ育休を取って、自分の考えに変化がありました。仕事は時間内に終わらせて、できるだけ残業しないで帰ろうという気持ちが強くなりました。また、保育参観などの子どもの行事については、男は仕事があるから参加しなくてもいいと思っていましたが、今はできるだけ参加したいと思うようになりました。
職場には大変迷惑をかけましたが、育児休業を取得できるきっかけを与えてくれた上司や同僚には、本当に感謝しています。
(上司の声)
昔とちがって、男性も積極的に育児に関わることが必要な時代になっているとつくづく感じます。職場の状況を考えると、正直なところ、彼が不在になることで業務調整に悩むこともありました。しかし、「ここはチーム力のみせどころ」ということで、みんなで話し合い、協力して乗り切ることができました。業務の見直しや効率化など、必要に迫られたおかげで改善できた部分も多くありました。職場に復帰してからの彼は、以前より積極的かつ責任感を持って仕事に取り組んでくれています。
(令和5年7月号 院内月報誌より抜粋)
Q2 行動計画における仕事と子育ての両立支援や働き方の見直しの取組みにおいて、職場内でどのような影響がありましたか。
A もともと女性職員の育休取得率は100%でしたので、男性の育休取得推進が課題と考え、法改正に合わせ、育児休業規程を整備すると共に、育児と仕事の両立を目的とした短時間正職員制度も新たに設けました。
育児休業制度のわかりやすい説明や、産後パパ育休を取得した男性職員へのインタビュー記事など、院内月報誌をとおして、育児休業に関する情報を積極的に発信し、周知を図りました。管理者に対しては、育児休業に備えて業務の見直しや業務分担の調整をお願いし、どうしても人手が不足する業務については、代替要員等の採用を行ったことで、育休取得者と現場双方の負担感軽減に繋がったと考えています。
これらの取り組みの結果、少しずつではありますが、男性職員の育休取得が促進され、2年間で対象者9名のうち6名(取得率66%)の男性職員が育児休業を取得しました。男性職員でもあたりまえに育児休業を取得できる環境が整ってきたように思います。
Q3 今後の子育て・次世代支援において会社で特に力を入れて取り組みたいことを教えてください。
A 今後予定されている育児・介護休業法の改正に向けて、育休取得促進の継続、保育園等の送迎に伴う出退勤時間の調整、子どもの病気等による急な休みに対応するための体制づくり等に力を入れて取り組む所存です。また、職員が安心して育児と仕事を両立できるよう、人事担当者による相談窓口の設置等、妊娠から復職までをサポートする体制を構築する予定です。柔軟な働き方を実現するための取り組みを推進し、全職員のワーク・ライフ・バランス実現を目指します。