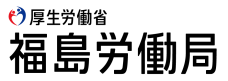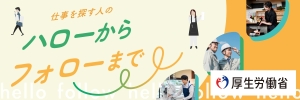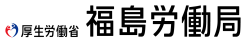- 福島労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労災保険関係 >
- 労災保険給付の内容
労災保険給付の内容
療養(補償)給付は、労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。
※「療養(補償)等給付の請求手続」パンフレットへ(厚生労働省HP)
(1)療養の給付
療養の給付は、被災労働者が労災病院や労災指定病院等において、無料で必要な治療などを受けることができる給付です。
労災病院又は労災指定病院等で無料で治療などを受けるためには、
・業務災害の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)
・通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)に所要事項を記入し、病院を経由して所轄労働基準監督署へ提出することになります。
(2)療養の費用の支給
療養の費用の支給は、労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療など受けた場合は、その治療などに要した費用を労働者本人が病院に支払い、その後所轄労働基準監督署に請求し現金給付を受けるものです。
所轄労働基準監督署に請求するためには、
・業務災害の場合は、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号)
・通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式16号の5)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署に提出することになります。
(3)支給の範囲
療養の給付及び療養の費用の支給の範囲は、(a)診察、(b)薬剤又は治療材料の支給(c)処置又は手術等の治療、 (d)入院、(e)訪問看護など、(f)移送のうち、政府が必要と認めるものとされています。
したがって、例えば一般に治療効果が認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要と認められないものなど一部支給されないことがあります。
労働者が業務上又は通勤による傷病のために休業し、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。その額は賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
休業(補償)給付を請求するためには、
・業務災害の場合は、「休業補償給付支給請求書」(様式8号)
・通勤災害の場合は、「休業給付支給請求書」(様式16号の6)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
※「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」パンフレットへ(厚生労働省HP)
(1)4日目
休業初日から3日間(=待期期間)については、休業日数に算入されず、その日数分の休業(補償)給付は支給されません。
なお、業務災害の場合はその3日間について事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。
(通勤災害の場合は、補償義務はありません。)
(2)給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、原則として災害が発生した日以前3ヵ月間に被災労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦の日数)で割った額です。
なお、給付基礎日額の最低保障額が決められおり、算定した給付基礎日額がその額に満たないときは、最低保障額が給付基礎日額として適用になります。
(注)通勤災害の場合は、一部負担金として200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額され、給付されることになります。
療養(補償)給付を受けている労働者の傷病が療養開始後1年6ヵ月経過しても治らず、傷病等級(第1級~第3級)に該当し、その状態が継続している場合に給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
※「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」パンフレットへ(厚生労働省HP)
傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害(補償)給付には、障害の程度に応じて障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。
障害(補償)給付を請求するためには、
・業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号)
・通勤災害の場合は、「障害給付支給請求書」(様式16号の7)に所要事項(医師の診断含む)を記入し、所轄労働基準監督署に提出することになります。
※「障害(補償)等給付の請求手続」パンフレットへ(厚生労働省HP)
(1)障害(補償)年金
障害等級第1級~第7級の場合に給付基礎日額の313日~131日分の年金が支給されます。
(注)同一事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されます。
(2)障害(補償)一時金
障害等級第8級~第14級の場合に給付基礎日額の503日~56日分の一時金が支給されます。
(3)障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が下表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対して支給されます。
障害(補償)年金差額一時金を請求するためには、「障害(補償)年金差額一時金支給請求書」(様式37号の2)に必要書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
(4)障害(補償)年金前払一時金
傷病が治ゆした直後において、被災労働者が社会復帰等を行うに当たって一時的に資金を必要とする場合は、障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ下表に掲げてある額の範囲以内で定めてある一定額をまとめて前払で受けられます。ただし、その場合前払一時金の額に達するまでの間、年金は支給停止されます。
障害(補償)年金前払一時金を請求するためには、「障害(補償)年金前払一時金請求書」(年金申請様式10号)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
| 障害等級 | 額 |
| 第1級 | 給付基礎日額の1,340日分 |
| 第2級 | 給付基礎日額の1,190日分 |
| 第3級 | 給付基礎日額の1,050日分 |
| 第4級 | 給付基礎日額の 920日分 |
| 第5級 | 給付基礎日額の 790日分 |
| 第6級 | 給付基礎日額の 670日分 |
| 第7級 | 給付基礎日額の 560日分 |
(5)「治ゆ」の考え方
傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になったときという意味ではなく、症状が安定し医学上一般に認められた医療行為を行っても、その医療効果が期待できない状態になったことをいいます。
例えば、
・骨折などの負傷の場合には、たとえなお疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養を継続しても改善が期待できないとき。
・疾病の場合には、急性症状が消退し、慢性症状は持続していてもその症状が安定し療養を継続しても医療効果が期待できないとき。
が「治ゆ」であるということになります。
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合にその遺族に支給されます。
遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金とがあります。
※「遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」パンフレットへ(厚生労働省HP)
(1)遺族(補償)年金
労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母孫、祖父母、兄弟姉妹の遺族が受給資格者となります。
この受給資格者のうちの最先順位者(受給権者)に年金が支給されることになります。
遺族(補償)年金を請求するためには、
・業務災害の場合は、「遺族補償年金支給請求書」(様式12号)
・通勤災害の場合は、「遺族年金支給請求書」(様式16号の8)に所要の書類を添えて、所轄労働基
準監督署に提出することになります。
(注)同一事由により厚生年金保険の遺族厚生年金等が併給される場合は一定の調整率によって調整され支給されます。
○遺族(補償)年金の支給額は次のとおりです。
| 遺 族 数 | 年 金 額 |
| 1 人 | 年金給付基礎日額の153日分 |
| 55歳以上の妻又は 厚生労働省令で定める 障害の状態にある妻 |
年金給付基礎日額の175日分 |
| 2 人 | 年金給付基礎日額の201日分 |
| 3 人 | 年金給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 年金給付基礎日額の245日分 |
(2)遺族(補償)一時金
労働者の死亡当時遺族(補償)年金の受給資格者がいないときには給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
受給資格のない遺族のうち最先順位者に支給されます。
遺族(補償)一時金を請求するためには、
・業務災害の場合は、「遺族補償一時金支給請求書」(様式15号)
・通勤災害の場合は、「遺族一時金支給請求書」(様式16号の9)
に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
(3)遺族(補償)年金前払一時金
労働者の死亡直後において一時的な出費を必要とする場合は、遺族(補償)年金受給者の請求に基づいて、年金給付基礎日額の1,000日分の額の範囲以内で定めてある一定額をまとめて前払で受けられます。 ただし、その場合前払一時金の額に達するまでの間、年金は支給停止されます。
遺族(補償)年金前払一時金を請求するためには、「遺族(補償)年金前払一時金請求書」(年金申請様式1号)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
死亡労働者の葬祭を行う者に支給されます。
葬祭料(葬祭給付)を請求するためには、
・業務災害の場合は、「葬祭料請求書」(様式16号)
・通勤災害の場合は、「葬祭給付請求書」(様式16号の10)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
葬祭料(葬祭給付)
=315,000円+給付基礎日数の30日分
又は
=給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
※「遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続」パンフレットへ(厚生労働省HP)
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の者又は第2級(精神・神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限る。)の者のうち、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
ただし、介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、特別養護老人ホームまたは原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所している方には支給されません。
介護(補償)給付を請求するためには、「介護(補償)給付支給請求書」(様式16号の2の2)に医師の診断書など必要な書類添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
※「介護(補償)等給付の請求手続」パンフレットへ(厚生労働省HP)
労働安全衛生法に基づいて行われる定期健康診断等のうち、直近のものにおいて、脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合に、二次健康診断等給付が受けられます。
二次健康診断等給付を請求するためには、「二次健康診断等給付請求書」(様式第16号10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、福島労働局へ提出することになります。
※「二次健康診断等給付の請求手続」パンフレットへ(厚生労働省HP)
〈給付の要件〉
(1)一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断されたときは二次健康診断等給付を受けることができます。
①血圧検査
②血中脂質検査
③血糖検査
④腹囲の検査またはBMI(肥満度)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により、①~④の検査項目において「異常なし」と診断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。
(2)脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
(3)労災保険の特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはなりません。