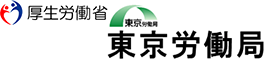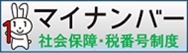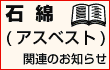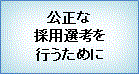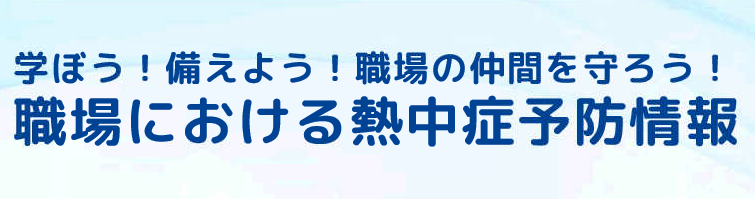- 東京労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 安全衛生関係 >
- 産業保健フォーラム IN TOKYO 2025基調講演・事例発表
産業保健フォーラム IN TOKYO 2025
基調講演・事例発表
※ 令和8年1月11日(日)までの期間限定公開です。ご好評につき公開期間を延長しました!
動画をご覧いただいた方におかれましては、アンケートにご協力をお願いします。
動画をご覧いただいた方におかれましては、アンケートにご協力をお願いします。
基調講演
■ 高年齢労働者のウェルビーイングと産業保健に求められる役割
法政大学キャリアデザイン学部教授
東京産業保健総合支援センター相談員
廣川 進 氏
略歴
法政大学キャリアデザイン学部教授、公認心理士、臨床心理士
大学卒業後、18年間(株)ベネッセコーポレーションに勤務し編集や人事を経験。大正大学博士課程(臨床心理学)修了。大正大学臨床心理学科教授を経て2018年4月から現職。海上保安庁(惨事ストレス・メンタルヘルス対策アドバイザー)、千葉県庁(復職支援プロジェクト)等の官公庁や民間企業で非常勤カウンセラーとして勤務。ストレスマネジメント、中高年のライフキャリアの研修講師等も行っている。
講演要旨
高年齢労働者が年々増加している。雇用者の60才以上の占める割合は約2割となり、さらに死傷者数(休業4日以上の死傷者数)では25%を超えている(14次防)。経験や技能の継承といった期待が高まる一方、安全・健康面での課題も顕在化している。「人的資本経営」、「ウェルビーイング経営」が広まりつつある中、労働者の安全衛生対策は人材確保、経営戦略につながるとして重要性が高まっている。
多様性に開かれた安全文化の職場風土の醸成、治療と仕事の両立支援、メンタルケア等、産業スタッフに求められる新たな役割を検討する。
事例発表
■ ①ケースに学ぶ高年齢労働者の健康保持・増進策と自職場への活用
産業医科大学 産業医実務研修センター副センター長 教育教授
柴田 喜幸 氏
講演要旨
高年齢労働者の安全・健康問題の予防・解決は、産業保健スタッフだけの努力では限界があり、「各職場が」「全員で」「常に」取り組み続けることが不可欠と考えます。
本講では、その考えを踏まえて実践された好事例のご紹介とともに、参加された皆さんが職場に帰りその知見を活用可能となるようなワークを行っていただきます。
それにより、単に「話を聞いて帰る」に留まらず、実効性の高い時間にしていただければと思っています。
一般的に高年齢者は脆弱性が高いと考えられます。転じて、このワークを活かした高年齢者対策を通じ、職場全体の産業保健のレベルアップの一助となれば幸いです。
■ ②人生100年時代の口の健康とは~歯だけではなく口の機能も重要です~
東京科学大学 大学院 医歯学総合研究科
地域・福祉口腔機能管理学分野 教授
松尾 浩一郎 氏
講演要旨
みなさんは、最近注目されている「オーラルフレイル」という言葉を聞いたことがありますか?加齢に伴う口の機能の些細な衰えのことを「オーラルフレイル」と呼びます。栄養摂取の入口である「口」の機能が衰えると、気づかないうちに、食事が偏り、生活習慣病やフレイル(身体の衰え)ひいては要介護の一因となると言われています。
いつまでも美味しくご飯を食べること、しっかり噛んで食べられる口の健康を維持することが、身体の健康を維持するために欠かせません。
今回は、口の機能とは?口の機能を維持するために大事なことは何か?について、われわれの取組を含めながらお話します。
■ ③企業における治療と仕事の両立支援~職場の環境整備の視点から~
公益財団法人 明治安田厚生事業団 ウェルネス開発室長
健康経営エキスパートアドバイザー
三橋 由美子 氏
講演要旨
厚生労働省のガイドラインをもとに、独自のガイドラインを作成するまでを振り返り、実際に制度を活用するには「自分ごと化」「見える化」が大切だと学ぶ。
健康経営を推進しながら職場環境の整備を行っているが、大前提として従業員の誰にとっても安全、安心な職場であるかどうかが問われる。
オリジナルな健康づくり施策を推進し、その成果をさまざまな企業や地域で実装することを目標としているので、私たちの職場自体がその範となるような仕組みづくりに取り組んでいる。
産業医科大学 産業医実務研修センター副センター長 教育教授
柴田 喜幸 氏
講演要旨
高年齢労働者の安全・健康問題の予防・解決は、産業保健スタッフだけの努力では限界があり、「各職場が」「全員で」「常に」取り組み続けることが不可欠と考えます。
本講では、その考えを踏まえて実践された好事例のご紹介とともに、参加された皆さんが職場に帰りその知見を活用可能となるようなワークを行っていただきます。
それにより、単に「話を聞いて帰る」に留まらず、実効性の高い時間にしていただければと思っています。
一般的に高年齢者は脆弱性が高いと考えられます。転じて、このワークを活かした高年齢者対策を通じ、職場全体の産業保健のレベルアップの一助となれば幸いです。
■ ②人生100年時代の口の健康とは~歯だけではなく口の機能も重要です~
東京科学大学 大学院 医歯学総合研究科
地域・福祉口腔機能管理学分野 教授
松尾 浩一郎 氏
講演要旨
みなさんは、最近注目されている「オーラルフレイル」という言葉を聞いたことがありますか?加齢に伴う口の機能の些細な衰えのことを「オーラルフレイル」と呼びます。栄養摂取の入口である「口」の機能が衰えると、気づかないうちに、食事が偏り、生活習慣病やフレイル(身体の衰え)ひいては要介護の一因となると言われています。
いつまでも美味しくご飯を食べること、しっかり噛んで食べられる口の健康を維持することが、身体の健康を維持するために欠かせません。
今回は、口の機能とは?口の機能を維持するために大事なことは何か?について、われわれの取組を含めながらお話します。
■ ③企業における治療と仕事の両立支援~職場の環境整備の視点から~
公益財団法人 明治安田厚生事業団 ウェルネス開発室長
健康経営エキスパートアドバイザー
三橋 由美子 氏
講演要旨
厚生労働省のガイドラインをもとに、独自のガイドラインを作成するまでを振り返り、実際に制度を活用するには「自分ごと化」「見える化」が大切だと学ぶ。
健康経営を推進しながら職場環境の整備を行っているが、大前提として従業員の誰にとっても安全、安心な職場であるかどうかが問われる。
オリジナルな健康づくり施策を推進し、その成果をさまざまな企業や地域で実装することを目標としているので、私たちの職場自体がその範となるような仕組みづくりに取り組んでいる。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康課
- TEL
- 03-3512-1616