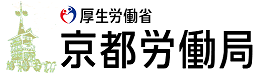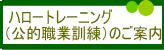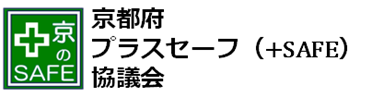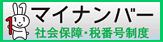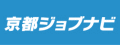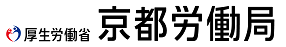求職中の方へ
ご覧になりたい分野名をクリックしてください。
職業紹介
- Q1. ハローワークで紹介してもらった事業所で面接を受けましたが、求人票に記載されている内容と条件が違いました。どこに相談すればいいですか。
- A1. ハローワークが紹介した求人の条件と会社の面接で説明を受けた条件が異なる場合の相談窓口は、紹介を受けたハローワーク、又はハローワーク求人ホットラインへお申し出ください。(ハローワークでは申し出に対応する担当者を設けています。また、ハローワーク求人ホットラインは、皆様からの申出を全国一元的に受け付ける専門の窓口です。)
お申し出をいただきましたら、求人を受理したハローワークと連携して、会社に事実確認と必要な指導などを行います。なお、お申し出をいただいた方のお名前を明らかにせず、会社に事実確認や必要な指導を行うことも可能です。
(参考)
※ 通話料金はご負担をお願いします。
ハローワーク求人ホットライン
- TEL
- 03(6858)8609
- 受付時間
- 8時30分~17時15分(土日祝・年末年始除く)
職業訓練
- Q1. ハローワークで行う職業訓練には、どのような種類がありますか。
- A1. 職業訓練には2種類あります。(1)公共職業訓練と(2)求職者支援訓練です。(1)の公共職業訓練は、雇用保険を受給している方を対象としており、(2)の求職者支援訓練は、主に雇用保険を受給できない方を対象としています。
ものづくり系(機械、建築、電気、溶接など)、事務系(パソコン操作(ワード・エクセルなど)、経理事務、医療事務など)、介護福祉など様々な訓練があります。
まずは、お近くのハローワークへお問い合わせください。 - Q2. 職業訓練受講を考えているのですが、相談・申込はどのようにすればよいでしょうか?
- A2. ハローワークの窓口の相談員が、あなたが希望する職種への就職に向けて、必要な職業訓練を一緒に考えていきます。
相談から訓練受講開始までは、職業訓練コースの選定、申し込み(願書の提出)、選考(筆記試験や面接試験など)を経て、訓練受講開始という流れになります。
お近くのハローワークへお問い合わせいただき、ご相談ください。
雇用保険
- Q1. 離職したため雇用保険を受給しようと思うのですが、制度と受給手続のあらましを教えてください。
- A1. 会社などで雇用されていた方が離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう、一定の要件を満たせば、雇用保険の基本手当を受けることができます。
雇用保険の基本手当は、雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%(60~64歳については45%~80%)です(上限額あり)。 - Q2. 私は、現在、基本手当を受給していますが、求人者の選考試験を受験するため、次回の失業の認定日にハローワークへ出頭することができません。このような場合、失業の認定を受けることができないでしょうか。
- A2. 失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた失業認定日以外には行えないこととなっていますが、受給資格者が「職業に就くためその他やむを得ない理由」のため、所定の失業認定日にハローワークに出頭できない場合には、受給資格者の申出により、安定所長が失業認定日を変更することができることになっています。なお、失業認定日の変更の申出は、原則として、事前にしなければならないこととなっていますが、変更理由が突然生じた場合で、あらかじめ申し出ることができなかった場合は、次回の所定認定日の前日までに申し出なければなりません。
ご質問のように、求人者の選考試験を受験するため、失業認定日に出頭できないことは、「職業に就くためその他やむを得ない理由」に該当しますので、その旨を申し出れば、失業認定日の変更の取扱いを受けることができます。
※ 詳細につきましては、ハローワークにご確認ください。