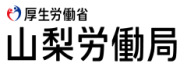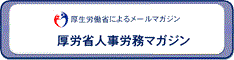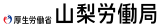制裁!
 |
A:相殺!賠償金!の時に、制裁はまた別に、というお話でした。 | |
 |
B:そうですね。少しおさらいをしてみましょうか。 |
|
 |
A:労働基準法では、就業規則で減給の制裁を定める場合には、1回の金額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならない、また、その総額が、1賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない、でしたよね。 | |
 |
B:そうですね。 | |
 |
A:平均賃金ってよくテレビなどでいわれているあれですか。 |
|
 |
B:おそらく、春闘結果や賃金引上げ報道の際に説明されているもののことを考えておられるのではないかと思いますが、それは、統計結果などから算出された賃金額のことで、労働基準法で定義されている平均賃金とは異なるものです。 | |
 |
A:ちょっと紛らわしいですね。 |
|
 |
B:そうですね。 労働基準法で定められている平均賃金は、算定する場合が決まっているので、その時の情報を確認して判断してもらうことになると思います。 |
|
 |
B:労働基準法で規定されている平均賃金は、原則的には、その事由の発生した日の直前3か月の総賃金をその3か月の暦日数で除したもののことです。 原則以外の平均賃金の計算方法についても、労働基準法第12条に規定されていますので、必要に応じて調べてみてください。 |
|
 |
A:総賃金というと、税金や社会保険料を控除する前の賃金のことですね。 | |
 |
B:はい。そのとおりです。 総支給額という場合もあると思います。 |
|
 |
A:一つの事由では平均賃金の半分までなんですね。 でも、もし、複数の事由で制裁を行う場合ではどうなんですか。 1日に2つの事由があれば1日分の平均賃金の半分の2倍ということになるんですか。 |
|
 |
B:そういうことです。 誤解のないように説明しますと、懲戒事由に該当する行為を行った日の賃金から「平均賃金の半額」の2倍を引く、ということではなく、一つの賃金締め切り期間の中の賃金から1日分の平均賃金の半額の2倍を引く、ということになると思います。 |
|
 |
A:もしも、たくさんの懲戒事由があった場合、その事由の回数に応じて平均賃金の半分を引いていったとすると、賃金総額の10分の1を超えてしまう場合はどうなんですか。 | |
 |
B:まずは、処分について考えてみましょうか。 一般に、就業規則での制裁の規定は、軽い方から、注意、訓告、戒告、減給、出勤停止、解雇のように、段階的になっていると思います。 |
|
 |
A:そう考えると減給っていうのは重い処分なんですね | |
 |
B:そうですね。 減給の制裁というのは、処分の中でも重いほうに入ると考えられるので、1か月に減給の制裁を受けるような不法行為をたくさん行う人はめったにいないと思われます。 でも、もし、万が一そのようなことがあれば、つまり、減給の制裁を行う事由が複数あって、当該賃金期間の賃金総額の10分の1を超えてしまうような場合、引けなかった部分は翌月に繰り越すことになると思います。 |
|
 |
B:制裁を行う場合に注意が必要な点がもう一つあります。 制裁としての減給を行う場合には、就業規則に制裁に関する規定を設ける必要があることに注意が必要です。 |
|
 |
A:就業規則って、10人以上の労働者を雇用している事業場で定めなくてはならないものでしたよね。 | |
 |
B:はい。 でも、ここでいう就業規則とは、労働基準法で定められている就業規則と、10人未満の労働者を使用している場合に定める社内の規則を含むと考えられています。 |
|
 |
A:つまり、根拠なく労働者に制裁を行うことはできない、ということなんですね。 | |
 |
B:そうですね。 制裁は、労働者に対して不利益な処分を行うわけですから、合理的な根拠が必要ということです。 |
|
 |
A:テレビや新聞で減給10分の1を6か月とか見るんですけど、規定さえ作れば、そのような制裁もできるのですか。 | |
 |
B:いいえ。 先ほども説明しましたように、労働基準法の適用がある労働者の場合、一つの事由で、制裁として減給できるのは平均賃金の半額まで、複数の事由で減額の制裁をする場合であっても、一賃金期間内では、賃金の総賃金の10分の1までということですから、減給10分の1を6か月のようなことはできません。 |
|
 |
B:たぶん、会社の社長が役員報酬の10分の1を返還するとか、労働基準法上の労働者ではない方の懲戒処分としての減給のことではないでしょうか。 もし減給10分の1を6か月も行ったとしたら、労働基準法違反で処罰される可能性があります。 さらに、制裁の事由があったとした場合でも、その事由が1回の場合には、制裁として減給した分のうち少なくとも平均賃金の半額を超える分、複数回の事由があった場合では一賃金支払い期における賃金の10分の1を超える金額について、労働者に返還しなければなりません。 |
|
 |
A:先ほど説明を聞いた、労働基準法は民法の特別法なので労働基準法で禁止されていることをしても、そのことが無効になるということなんですね。 | |
 |
B:そうですね。 |
|
 |
A:会社内における不法行為で、降格されたりすることもあると思いますが、降格されると当然賃金も下がりますよね。 それも減額の制裁に該当するのですか。 |
|
 |
B:仕事の内容が変わるような降格や異動により、賃金額が下がるというのは、仕事内容の変更に伴う賃金額の変更であるため、減給の制裁には当たらないとされています。 | |
 |
A:遅刻や欠勤の場合、賃金が減額されることがありますが、これも減給の制裁になるのですか。 | |
 |
B:賃金の原則は「ノーワーク、ノーペイ」で、働いてない部分については支払わなくてもよいので、遅刻や欠勤分だけを賃金から差し引いたとしても、減額の制裁とはなりません。 ただし、差し引かれる額が遅刻や欠勤分を少しでも超えた場合、それがたとえ1円でも、その超えた分は減給の制裁になると考えられます。 もっとも、たった1回の遅刻で減給の制裁を行った場合、その処分が合理的かどうかについても、疑問が残りますね。 このあたりのことは、民事的なことですので、ケースバイケースということになるでしょう。 |
|
 |
A:なるほど。その前に、遅刻や無断で欠勤しないように口頭で注意するとか、文書で注意するとかして、再度の欠勤や遅刻を防止する必要があるということなんですね。 では、出勤停止はどうですか。 出勤停止だって、停止中は給料出ないのですから、同じようなことですものね。 |
|
 |
B:減給の制裁と出勤停止で賃金が支払われないことは少し違うと考えられています。 まず、出勤停止の場合、処分は出勤停止です。 「ノーワーク、ノーペイ」ですから、出勤停止により賃金は支払われなくなるのですが、これについては、出勤停止に基づく結果であると解されていて、減給の制裁とは関係がないとされています。 |
|
 |
A:制裁になったりならなかったり、いろいろな場合が考えられるのですね。 制裁は、就業規則への記載は必要ということでしたね。 |
|
 |
B:そうですね。 労働基準法では、制裁の規定は相対的必要記載事項とされていますので、会社で制裁の規定を設けないこともできます。 しかし、制裁の規定がない場合には、会社は労働者に対して制裁をすることはできませんので、制裁を行う可能性がある場合には、制裁の規定を設ける必要があります。 また、制裁の規定が合理的ではない場合、制裁の規定そのものが無効とされる場合もあります。 就業規則に制裁の規定を入れるかどうか、またどのような制裁規定とするかについては十分検討する必要があるでしょう。 |
|
 |
||