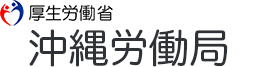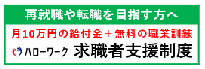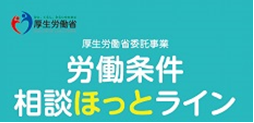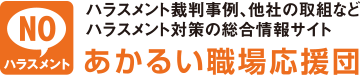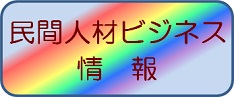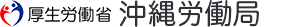- 沖縄労働局 >
- 法令・制度・施策・手続き >
- 労働条件・労働契約 >
- 就業規則 >
- 就業規則の作成について
就業規則の作成について
明るい職場を作るため、就業規則を作成していますか?
労働基準法では、パートタイマー等を含め常時10人以上の従業員を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることを義務付けています。
なお、従業員10人未満の事業場でも、就業規則を作成整備することが望まれます。
就業規則の作成や変更に当たっては、次のことに注意しましょう。
- 1.就業規則の記載事項は、労働基準法第89条で具体的に定められています。
- 2.就業規則を作成又は変更する際は、事業場の従業員の過半数で組織する労働組合、それが5ない場合は、適正な手続きで選ばれた従業員の過半数代表者の意見を聴くとともに、その意見書を添付した就業規則を、最寄りの労働基準監督署長に届け出る必要があります。(同法第90条)
- 3.就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。(同法第92条)
- 4.就業規則は、事業場に働くすべての従業員に適用される必要があります。
- 5.就業規則は、従業員と事業主の双方を拘束するため職場の実態にあわないと、
かえってトラブルの原因となりかねませんので、各職場の実態に合った内容とする必要があります。 - 6.就業規則は、従業員と事業主の双方を拘束するため職場の実態にあわないと、
かえってトラブルの原因となりかねませんので、各職場の実態に合った内容とする必要があります。
就業規則の記載事項必ず記載すべき事項
(絶対的必要記載事項)
- 1.労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合の就業時転換。 - 2.賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給(臨時の賃金等を除く) - 3.退職関係
退職の事由(解雇を含む)とその手続き等。
制度を設ける場合、就業規則に記載すべき事項
(相対的必要記載事項)
- 4.退職手当関係
退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期 - 5.臨時の賃金等及び最低賃金額
- 6.食費、作業用品その他の負担
- 7.安全衛生
- 8.職業訓練
- 9.災害補償及び業務外の傷病扶助
- 10.表彰及び制裁の種類及び程度
- 11.その他当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合は、これに関する事項
※これ以外に、任意に就業規則に規定する事項(任意記載事項)もあります。
労働契約や労働時間など働き方に係るルールを整備する「労働基準法の一部を改正する法律」(平成15年法律第104号)が公布(平成16年1月1日施行)されました。この中で、就業規則の絶対的必要記載事項である「退職に関する事項」に「解雇の事由」を記載する必要があることが義務付けられました。
1. 解雇
近年、解雇をめぐるトラブルが増大しており、その防止・解決には、解雇に関する基本的なルールを明確にすることが必要となっています。そこで、最高裁の判決で確立しているものの、これまで労使当事者間に十分に周知されていなかった「解雇権濫用法理」(※)が法律に明記されました。すなわち、第18条の2として、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
との規定が新設されました。
※「解雇権濫用法理」とは、昭和50年の最高裁判決において示されたものです。この判決では
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる。」
と判示されています。
2. 解雇理由の明示
(第22条第2項)
解雇をめぐるトラブルを未然に防止し、その迅速な解決を図るために、これまでの退職時証明に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求できることになりました。ただし、使用者は、解雇の予告がされた日以後に労働者がその解雇以外の事由によって退職した場合は、この証明書を交付する義務はありません。
3.就業規則への「解雇の事由」の記載
(第89条第3号)
労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載することが必要になりました。
〈注〉既に作成している就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載していない場合には「解雇の事由」を記載した上で、改めて、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
記載例は、以下のとおりです。
就業規則における解雇に係る規定のモデル
(モデル就業規則から抜粋)
(普通解雇)
第○○条
| 1. | 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。 | ||
| ① | .勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき | ||
| ② | 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき | ||
| ③ | 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合であって、 従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。) |
||
| ④ | 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたとき | ||
| ⑤ | 試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき | ||
| ⑥ | 第△△条に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたとき | ||
| ⑦ | 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき | ||
| ⑧ | 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき | ||
| ⑨ | その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき | ||
| 2. | 前項の規定により従業員を解雇する場合は、 少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、 労働基準監督署長の認定を受けて第△△条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。 |
||
| ① | 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用される者を除く。) | ||
| ② | 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用される者を除く。) | ||
| ③ | 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く。) | ||
| 3. | 第1項の規定による従業員の解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。 | ||
【第○○条の解説】
| 1. | 本条第1項は、就業規則に定められる解雇の事由についての規定です。就業規則における解雇の事由については、平成16年1月1日から施行された改正労働基準法において、労働基準法第89条第3号に定める「退職に関する事項」には、「解雇の事由」が含まれることが明らかにされたところです。労働基準法第89条第3号は、就業規則の作成に際し、必ず記載することが必要な事項を規定したものですから、同号に含まれる解雇の事由については、必ず就業規則に規定することが必要です。 | ||
| 2. | 解雇の事由について、その事由ごとに大別すると、一般的には、 | ||
| ① | 労働者の労務提供の不能、労働能力又は適格性の欠如・喪失によるもの(本条第1項1,から5,まで) | ||
| ② | 労働者の規律違反の行為によるもの(本条第1項6),) | ||
| ③ | 経営上の必要性によるもの(本条第1項7), 及び8), )に分けられ、本条においては、この分類に沿った具体的な規定例を掲げていますので、各事業場において、解雇の事由を定める際の参考としてください。 | ||
| 3. | 上記2の2), の労働者の規律違反の行為による解雇の事由については、本条第1項6), においては、「第△△条に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたとき」としていますが、これらの事由を必ずしも懲戒解雇の事由としなければならないものではなく、各事業場の実情に応じて、普通解雇の事由としてのみに規定することも差し支えありません。 | ||
| 4. | 本条第1項3), については、試用期間中の労働契約は、解約権留保付労働契約であって、最高裁判決において、「このような留保解約権に基づく解雇は通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められてしかるべき」と判示(三菱樹脂事件最高裁大法廷判決日昭和48年)されていることにかんがみて、この規定を設けているものですが、試用期間を設けるか否か、また、試用期間中の労働契約をどのような契約内容とするかは、各事業場の実情に応じて定められるものであり、必ずしも5), のような規定を設けなくとも差し支えありません。 | ||
| 5 | 本条第1項9), については、いわゆる包括条項と呼ばれる規定で、就業規則を作成する時点では想定できないような事情であって、かつ、他の事由との比較衡量からして、解雇に処することが必要である場合が発生する可能性があることを想定して規定しているものです。解雇に至るまでの事情は千差万別であり、それらをすべて網羅的に規定することは困難であるため、解雇の事由の中にこのような包括条項の規定を置くことはやむを得ないことではありますが、解雇に際しての労使間のトラブルを防止する観点からは、他の解雇の事由をできる限り明確かつ網羅的に規定し、包括条項が適用される範囲をより限定することが適当です。 | ||
| 6. | なお、労働基準法第89条には、就業規則に規定する解雇の事由の内容について、特段の制限はありませんが、改正労働基準法において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働基準法第18条の2)こととされたところです。 また、労働基準法をはじめとした各法律(下記参照)においては、以下に掲げる場合の解雇が禁止されていますので、就業規則に解雇の事由を定めるに当たっては、これらの法律の規定に抵触しないものとすることが必要となります。 | ||
※解雇が禁止されている場合
- 1.従業員の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
- 2.従業員の業務上の負傷、疾病による休業期間とその後30日間及び産前産後の休業の期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内又は産後8週間以内の女性が休業する期間)とその後30日間の解雇
(労働基準法第19条) - 3.従業員が労働基準監督機関に申告したことを理由とする解雇
(労働基準法第104条、労働安全衛生法第97条) - 4.従業員が女性であること、女性従業員が結婚、妊娠、出産し、又は産前産後の休業をしたことを理由とする解雇、労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職及び解雇にかかる男女の均等な機会及び待遇の確保にかかる労使の紛争について都道府県労働局長に援助をもとめたこと又は労働者の配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職及び解雇にかかる男女の均等な機会及び待遇の確保に係る労使の紛争について都道府県労働局長に調停の申請をしたことを理由とする解雇
(男女雇用機会均等法第8条、第13条2項、第14条2項) - 5.従業員が都道府県労働局長に個別労働関係紛争に関し、その解決の援助を求めたことを理由とする解雇
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条) - 6.従業員が育児休業及び介護休業の申出をしたこと、又は育児休業及び介護休業をしたことを理由とする解雇
(育児・介護休業法第10条及び第16条) - 7.従業員が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又は労働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働組合法第7条)等
2, においては、天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合、又は業務上の事由による負傷、疾病の従業員が療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又はその日以降、同年金を受けることになった場合)については、解雇の制限がありません。
これらの法律については、2, 及び4, の一部を除いて、解雇のみならず、これらを理由とする不利益取扱いも禁止されています。
- 8.従業員を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です。ただし、解雇予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます。
- 9.改正労働基準法においては、従業員を解雇する場合に、解雇予告の日から当該解雇による退職の日までに、解雇を予告された従業員から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書の交付をしなければならないこととなりました(労働基準法第22条第2項)。
また、解雇後に、解雇された従業員から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合についても、遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書の交付をしなければならないことは従来と変わりがありません(労働基準法第22条第1項)。 - 10.障害者の雇用については、「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努カに対して協力する責務を有するものであって、その有する能カを正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない(障害者の雇用の促進等に関する法律第5条)」こととされています。
また、同法により定められた障害者雇用対策基本方針においては、事業主が、障害者の障害の種類及び程度を踏まえ、配慮すべき事項が示されていますので、本条第1項3), については、これらの法律等の趣旨を踏まえた対応を前提として検討してください。
(懲戒の事由)
第△△条
| 1. | 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。(次のいずれか略) | ||
| 2. | 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。この場合において、行政官庁の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する予告手当は支給しない。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第○○条に定める普通解雇又は減給若しくは出勤停止とすることがある。 | ||
| ① | 重要な経歴を詐称して雇用されたとき | ||
| ② | 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき | ||
| ③ | 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき | ||
| ④ | 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき | ||
| ⑤ | 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき | ||
| ⑥ | 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。) | ||
| ⑦ | 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき | ||
| ⑧ | 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないと認められたとき | ||
| ⑨ | 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、又はその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき | ||
| ⑩ | 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき | ||
| ⑪ | 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき | ||
| ⑫ | 私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき | ||
| ⑬ | 会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき | ||
| ⑭ | その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき | ||
| 3. | 第2項の規定による従業員の懲戒解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する。 | ||
【第△△条の解説】
| 1. | 本条は、懲戒の事由を二つに分け、第1項において、「けん責、減給、出勤停止」とする場合の事由を、第2項において、「懲戒解雇」とする場合の事由を定めています。 | ||
| 2. | 懲戒処分については、労働基準法第89条第9号により、「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項」を定めていない場合には、同条違反となります。 また、最高裁判決(国鉄札幌運転区事件最高裁第3小法廷判決 昭和54年10月)において、懲戒処分について、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられていることから、就業規則に定めのない事由による懲戒処分は、懲戒権の濫用と判断されることになります。なお、懲戒の事由の内容については、労働基準法上では、特段の制限はありませんが、当該懲戒の事由に合理性がない場台には、当該事由に基づいた懲戒処分は、懲戒権の濫用と判断されることになるものと考えられます。 |
||
| 3. | 懲戒処分の種類については、けん責等の本条第1項及び第2項に掲ける処分の種類に限定されるものではなく、事業場の都合に応じて公序良俗に反しない範囲でその種類を定めることが可能ですが、減給処分については、就業規則で、減給の制裁を定める場合において、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないこととされている(労働基準法第91条)ほか、懲戒解雇については、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働基準法第18条の2)こととされています。 | ||
| 4. | 懲戒の対象者に対しては、規律違反の程度に応じて過去の同種の事例における処分の程度等を考慮して公正な処分を行うことが必要となります。裁判においては、使用者の行った懲戒が公正な処分でないと認められる場合には、当該懲戒処分について、懲戒権の濫用として、無効と判断されています。 | ||
| 5 | 懲戒解雇の事由について、事由ごとに大別すると、一般的には | ||
| ① | 経歴詐称/本条第2項1), | ||
| ② | 経歴詐称/本条第2項1), | ||
| ③ | 業務命令違反/本条第2項4), | ||
| ④ | 業務妨害/本条第2項5), | ||
| ⑤ | 職場規律違反/本条第2項5), から12),まで | ||
| ⑥ | 私生活上の非行等/本条第2項12), | ||
| ⑦ | 誠実義務違反/本条第2項13), | ||
| 6. | 本条第2項14), については、いわゆる包括条項と呼ばれる規定で、就業規則を作成する時点では想定できないような事情であって、かつ、他の事由との比較衡量からして、懲戒解雇に処することが必要である場合が発生する可能性があることを想定して規定しているものです。 懲戒解雇処分に至るまでの事情は千差万別であり、それらをすべて網羅的に規定することは困難であるため、懲戒解雇の事由の中にこのような包括条項の規定を置くことはやむを得ないことではありますが、懲戒解雇に際しての労使間のトラブルを防止する観点からは、他の懲戒解雇の事由をできる限り明確かつ網羅的に規定し、包括条項が適用される範囲をより限定することが適当です。 |
||
| 7. | 改正労働基準法においては、従業員を解雇する場舎、解雇予告の日から当該解雇による退職の日までに、解雇を予告された従業員から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場含は、遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書の交付をしなければならないこととなりました(労働基準法第22条第2項)。 また、解雇後に、解雇された従業員から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合についても、遅滞なく、当該解雇の理由を記載した証明書の交付をしなければならないことは従来と変わりがありません(労働基準法第22条第1項)。 |
||
<注>
「解雇の理由を記載した証明書」及び「退職の事由を記載した証明書」のモデル様式については、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。
御不明の点などがありましたら、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。