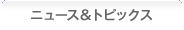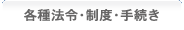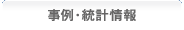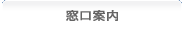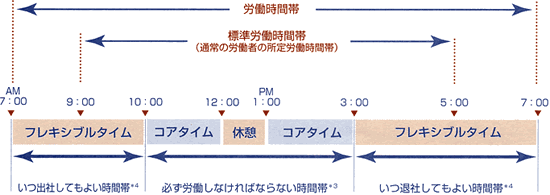■ 1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5) フレックスタイム制(第32条の3)
 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5) |
|
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
|
|
|
■
|
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、
|
 |
(1)
|
労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例事業も同じ)以下になるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること
|
| |
(2)
|
労使協定を所定の様式により、所轄の労働基準監督署に届け出ること
|
 |
が必要です。
|
|
| フレックスタイム制(第32条の3) |
|
フレックスタイム制とは、3ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
|
|
|
■
|
フレックスタイム制を採用するには、
|
 |
(1)
|
就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定すること
|
| |
(2)
|
労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(*1)、清算期間中の総労働時間(*2)、標準となる1日の労働時間などを定めること
|
 |
が必要です。
|
|
|
*1
|
清算期間
|
 |
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、1ヵ月以内とされています。1ヵ月単位のほかに、1週間単位等も可能です。
|
|
*2
|
清算期間中の総労働時間
|
| |
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。
|
|
*3
|
コアタイム
|
| |
労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。
|
|
*4
|
フレキシブルタイム
|
| |
労働者がその選択により労働することができる時間帯です。
|
|
|
|
(注1) 時間外労働となる時間
|
| |
フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働については、1日、1週間ではなく、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働となります。
時間外労働の労使協定についても、清算期間を通算して時間外労働することができる時間だけを協定すればよいことになっています。
(注2)清算期間が1か月を超える場合(2019年4月1日施行)
2018年の労働基準法の改正により、フレックスタイムの清算期間の上限が従来の1か月から3か月に延長されました。清算期間が1か月を超える場合は、当該清算期間を1か月ごとに区分した期間ごとに当該各期間を平均し、1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内で労働させなければなりません。
また、1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間について、当該月における割増賃金の支払いが必要となります。
さらに、清算期間が1か月を超える制度を採用する場合は、制度の内容を定めた労使協定を所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。
[フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(2019/2掲載)[3,804KB]]
|
|


 (更新アイコン)をクリックするか、または「F 5」を押してしてください。
(更新アイコン)をクリックするか、または「F 5」を押してしてください。