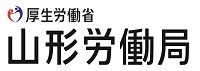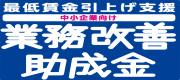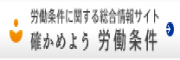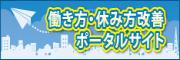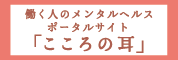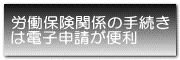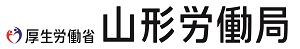- 山形労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 発表資料 >
- 2025年度 >
- 食料品製造業での災害増加が顕著に ~山形県内の令和6年労働災害発生状況(確定)まとまる~
食料品製造業での災害増加が顕著に ~山形県内の令和6年労働災害発生状況(確定)まとまる~
【照会先】
山形労働局労働基準部健康安全課健康安全課長 阿久津 拓也
主任地方産業安全専門官 木村 勝則
TEL 023-624-8223
山形労働局(局長 島田 博和)は、令和6年(1月から12月)に山形県内で発生した労働災害の発生状況を取りまとめましたので公表します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 令和6年の労働災害発生状況
| ◎ | 休業4日以上の労働災害による死傷者数は1,444人で、前年と比較して182人(11.2%)の減少となった。死亡者数は6人(製造業2人、建設業、陸上貨物運送事業、小売業、その他事業で各1人)で、前年同数となり、平成29年と令和5年と並び過去最少。平成28年以降一桁を維持している。(資料1、2) | ||
| ◎ | 新型コロナ関連を除く休業4日以上の労働災害による死傷者数は1,201人で、前年と比較して79人(6.2%)の減少となった。(資料3) | ||
| ◎ | 新型コロナ関連を除く死傷者数を業種別でみると、前年と比較して、製造業で2.8%の増加、建設業で18.6%の減少、運輸業で11.3%の減少(うち、陸上貨物運送事業は7.2%の減少)、商業で7.6%の減少(うち、小売業は5.0%の減少)、保健衛生業で8.7%の減少(うち、社会福祉施設は8.8%の減少)、接客娯楽業で4.6%の増加となった。 全体的に減少傾向にある中、製造業や接客娯楽業で増加しており、特に製造業のうち、食料品製造業における増加が著しい(前年と比較して21人(23.3%)増加)。(資料3) |
||
| ◎ | 新型コロナ関連を除く、食料品製造業における労働災害発生状況については、令和6年において休業4日以上の死傷者数は111人(前年比21人(23.3%)の増加)となっており、また全産業(1,201人)における構成比は9.2%であって、製造業の中では一番高い。 事故の型別では、「転倒」及び「動作の反動、無理な動作」といった労働者の動作に起因する「行動災害」が46人で41.4%を占めるほか、「はさまれ、巻き込まれ」、「切れ、こすれ」及び「高温の物との接触」の合計が37人で33.3%を占めている。 起因物別では、「転倒」の主な原因となっている「仮設物、建築物、構築物等」が31人(27.9%) と最も多い。また、食品加工用機械等(*1)による「はさまれ、巻き込まれ」、「切れ、こすれ」及び「高温の物との接触(やけど)」による災害が34人(30.6%)となっており、同起因物(37人)の9割以上(91.9%)となっている。 特に、食品加工用機械等を起因物とした「はさまれ、巻き込まれ」は6人の増加(前年14人)、「切れ、こすれ」も6人の増加(同2人)、「高温の物との接触」も6人の増加(同0人)となっている。 令和6年に発生した食料品製造業における食品加工用機械等を起因物とする死傷者数(34人) のうち、被災労働者の経験年数が0~2年未満が占める割合は41.2%、0~5年未満にあっては70.6%を占めており、また、被災労働者の年代別においては50代以上の割合が47.1%を占めている。 このような結果から、食料品製造業では「行動災害」に対する防止対策の徹底のほか、食品加工用機械等に対するリスクアセスメントを実施し、その結果に基づく対策を確実に講じることや、経験年数が5年未満である労働者に対する作業手順に関する安全教育を、雇入れ時はもとより、その後も定期に実施することが今後の労働災害の減少に有効であると判断される。 (資料3、4) |
||
| ◎ | 全業種を事故の型別でみると、「転倒」による災害が最も多く、全体の23.5%となっている。 また、「動作の反動・無理な動作」は14.5%となっており、これら「行動災害」によるものが全体の約4割(38.0%)を占めている。また、「墜落・転落」が13.4%と依然として多く発生した。(資料5) |
||
| ◎ | 「転倒」及び「動作の反動、無理な動作」といった労働者の作業行動に起因する「行動災害」が近年、全国的にも増加傾向にあり、「行動災害」に対する対策が重要となっている。 また、新型コロナ関連を除く死傷者数を年代別にみると、60代以上の者が占める割合が増加傾向にあり、高年齢労働者を対象とした労働災害防止対策の取組も重要となっている。 (資料6、7) |
||
| ◎ | 業種別の事業場規模別では、全産業において規模50人未満の事業場が 58.0%を占めており、また経験年数別では、全産業において経験10年未満の被災労働者が、全体の61.0%を占める。 さらに年齢別では、全産業において年齢50 代以上の被災労働者が全体の 53.9%を占める。 月別の死傷者数においては、最も多い月が3月(154 人)で、次いで8月(149 人)であった。 (資料8、9) |
||
| (*1) 「食品加工用機械等」とは、混合機(ミキサー)、食品製造用ロール機、成形機、切断機(スライサー)、熱による加工機械のほか、食品包装機械や食品製造ラインにおけるコンベア、手工具(包丁等)、用具(鍋等)を含む。 |
2 今後の主な取組
山形労働局では、令和5年3月に策定した「山形労働局第 14 次労働災害防止計画」(下表参照) に基づき、職場における安全衛生対策の更なる推進を図るため、事業場、関係機関等と連携を図りながら安全衛生対策の周知啓発、指導のほか、以下の取組を行うこととしている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | 令和6年における食料品製造業での労働災害発生状況を踏まえ、当局独自の労働災害を減少させるための中期的な取組を行う。 | ||
| ◎ | 上記、「第14次労働災害防止計画」として取組む転倒災害対策を含め、全業種において多発する労働者の作業行動に起因する「行動災害」について、当該災害の防止対策の取組の重要性について県内の各事業場に対し周知を行う。 特に冬期間における転倒災害防止のため、12/1~翌年2月末までの期間において「冬の労災をなくそう運動」を展開する。 |
||
| ◎ | 当局管内において令和5年より2年続けて熱中症による死亡災害が発生している。 これまでのWBGT値(暑さ指数)の活用やWBGT値の低減を図るための作業環境管理等の対策をはじめ、令和7年6月1日に施行される改正労働安全衛生規則により、職場における熱中症対策の強化が図られることから、県内の各事業場に対しあらゆる機会を通じて同対策の積極的な取組について広く周知徹底していく予定である。(資料 10) |
資料1 労働災害の推移
資料2 過去10年間の業種別労働災害発生状況
資料3 令和6年山形県内における労働災害発生状況(確定)
資料4 令和6年食料品製造業 労働災害発生状況
資料5 事故の型・起因物別死傷者数
資料6・7 行動災害発生状況の推移・高年齢労働者による労働災害の推移
資料8・9 業種別の事業場規模別、経験年数別、年齢別の割合・令和6年 月別の死傷者数
資料10 リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」
報道発表資料(令和7年5月1日)