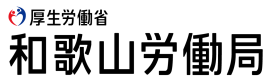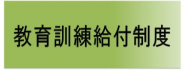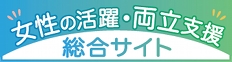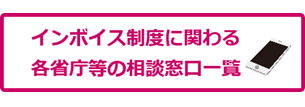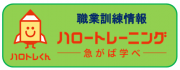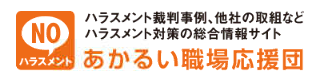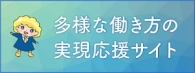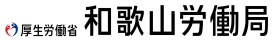- 和歌山労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 法令・制度 >
- 労災保険 >
- 脳・心臓疾患の労災認定
脳・心臓疾患の労災認定
はじめに
最近、生活習慣病とされる「がん」、心筋梗塞などの「心疾患」、脳梗塞などの「脳血管疾患」による死亡が増加しています。このうち、脳や心臓の疾患を原因とするものは、国民の死亡者の3割を占めるに至っています。
これらの脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる血管病変等が、主に加齢、食生活、生活環境などの日常生活による諸要因や遺伝等による要因により徐々に増悪して発症するものですが、仕事が主な原因で発症する場合もあります。これらは「過労死」とも呼ばれます。
厚生労働省は、これまで脳・心臓疾患の労災認定に当たって、主として発症前1週間程度の期間における業務量、業務内容等を中心に業務の過重性を評価してきましたが、平成13年12月、長期間にわたる疲労の蓄積についても業務による明らかな過重負荷として考慮することとし、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」(以下「脳・心臓疾患の認定基準といいます。)が改正されました。