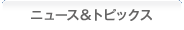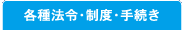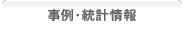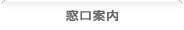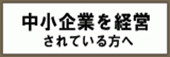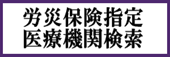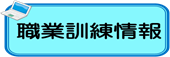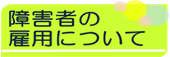職場の労務管理に関するQ&A
年次有給休暇編
|
Q1. |
当社は、従業員5名の零細企業ですが、それでも従業員からの請求があれば年次有給休暇を与えなくてはなりませんか? |
|
|---|---|---|
| A1. | 年次有給休暇は、事業場の業種、規模に関係なく、全ての事業場の労働者に適用されます。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強行法規ですので、年次有給休暇の制度を設けないことはできません。(労働基準法第39条) | |
|
Q2. |
年次有給休暇は、労働者を雇い入れた後、いつから与えなければなりませんか? |
|
|---|---|---|
| A2. | 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与する必要があります。付与日数は、初年度は10労働日ですが、通常の労働者と比較して労働日数が少ない場合(労働日数が週4日以下など)は、比例付与として10日より少ない日数となります。その後は、1年毎に8割以上出勤した場合は、法令で定められた日数を付与することになります。 | |
|
Q3. |
当社では、正社員には年次有給休暇制度がありますが、パート、アルバイトにはありません。このような取扱いでよろしいでしょうか? |
|
|---|---|---|
| A3. | 労働基準法上、パート、アルバイトも労働者であることから、正社員と同様に年次有給休暇を付与しなければなりません。但し、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下の労働者(パート、アルバイトなど)については、労働日数に応じて付与日数は少なくなります。ちなみに、初年度に発生する有給休暇日数は、6か月継続勤務、全労働日の8割以上の出勤を条件として、一般労働者10日、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週4日の労働者(パート、アルバイトなど)は7日などとなっています。 | |
|
Q4. |
年次有給休暇は1年間のうちに使用しないと消滅してしまうのですか。 |
|
|---|---|---|
| A4. | 付与された年次有給休暇の権利については、2年間行使しなければ時効により消滅します。よって、その1年間に取得できなかった年次有給休暇は、次年に限り繰り越すことになります。(労働基準法第115条) | |
|
Q5. |
従業員から年次有給休暇が請求されました。しかし、仕事が忙しいので今休ませると困ります。有給休暇の請求を断ることはできるのでしょうか? |
|
|---|---|---|
| A5. | 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求した時季に与えなければなりません。但し、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができるとされています(時季変更権)。「事業の正常な運営を妨げる」とは、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断されるべきものとされており、判例等の動向をみると、事業の正常な運営を妨げるかどうかは極めて限定的に解されており、従業員の大半が同時に請求してきた場合は格別、そうでない限りは与えなくてはならないと考えた方がよいと思われます。なお、会社が、労働者から請求があったにもかかわらず、有給休暇を与えない場合は、法律違反となります。 | |
|
Q6. |
1か月後に退職を控えた従業員が、「退職日までは残った有給休暇を全て使い、出勤しない」と言い出しました。引き継ぎの問題もあり、大変困っていますが認めなくてはなりませんか。 |
|
|---|---|---|
| A6. | 従業員からの年次有給休暇の請求(時季指定)に対し、会社には「時季変更権」がありますが、退職する従業員にはこれを行使する余地はありませんので、法律的には認めなくてはならないという結論になります。会社の実情を十分従業員に伝え、理解を得ることしか方法はないと思われます。 | |
|
Q7. |
年次有給休暇を使用し休暇を取得した場合、その日についていくら支払えばよいのですか? |
|
|---|---|---|
| A7. | 就業規則などで規定することとなっておりますが、支払わなければならない額は、「平均賃金」あるいは「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」のどちらかです。例外的に、労使協定により「健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額」にすることも可能です。(労働基準法第39条) | |
|
Q8. |
年次有給休暇を取得すると、「皆勤手当」がもらえなくなります。こんなことは許されるのですか? |
|
|---|---|---|
| A8. | 結論から申し上げれば、皆勤手当は支給しなければなりません。労働基準法附則第136条では、「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定め、「精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること。」としています。 | |
|
Q9. |
年次有給休暇の「買上げ」をしても法律違反にはなりませんか? |
|
|---|---|---|
| A9. | 労働基準法では、「(有給)休暇を与えなければならない。」と規定していますので、金銭を支給しても与えたことにはなりません。また、買上げの予約をして請求できる年次有給休暇日数を減らしたり、請求された日数を与えないことはできません。ただし、法を上回る日数の年次有給休暇については、この限りではありません。(労働基準法第39条) | |
|
Q10. |
欠勤した労働者から、「昨日の欠勤を年次有給休暇扱いにしてほしい」と言われました。有給休暇としなければなりませんか? |
|
|---|---|---|
| A10. | 年次有給休暇は、事前に請求するのが原則ですので、年次有給休暇とする義務はありません。しかし、事後に請求されたものについても、労使双方が年次有給休暇処理することで合意した場合は、年次有給休暇扱いとしても差し支えありません。 | |
|
Q11. |
定年退職された労働者を引き続き「嘱託」として雇用しましたが、その際、年次有給休暇はどうなるのですか? |
|
|---|---|---|
| A11. | 定年退職者の嘱託としての再雇用や臨時工の本採用等は、企業内における身分の切替えであって、実質的には労働関係が継続していると認められます。したがって、定年退職者を引き続き嘱託として使用している場合や臨時工を本採用として引き続き使用する場合は、勤務年数を通算しなければなりません。退職金を清算したうえで一旦全員解雇し、その直後に一部労働者を再雇用して事業を再開しているような場合についても同様に、実質的に労働関係が継続しているものと認められ、年次有給休暇の付与については、勤務年数を通算しなければなりません。 | |
|
Q12. |
各従業員に付与している年次有給休暇と年末・年始の休暇を合わせて10連休にしようと考えています。その場合の手続きについて教えて下さい。 |
|
|---|---|---|
| A12. | 年次有給休暇は、労働者が指定した時季に付与するのが原則ですが、労働時間短縮の面から、ご質問のような手法は有効と思われます。労働基準法においては、各従業員に付与している有給休暇日数の内、5日を超える部分については、計画的付与が認められています。その場合、所轄労働基準監督署長への届出は必要ありませんが、計画的に付与する時季等に関して「労使協定」を締結しておかなければなりません。(労働基準法第39条) | |
|
Q13. |
フレックスタイム制における年次有給休暇の取扱いについて教えてください。 |
|
|---|---|---|
| A13. | フレックスタイム制においても、年次有給休暇は与える必要があります。年次有給休暇を取得したときの賃金の算定基礎となる労働時間については、「フレックスタイム制のもとで労働者が年次有給休暇を取得した場合には、当該日に標準となる1日の労働時間労働したものとして取り扱うこととなる。」と通達されており、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」を決め、その時間労働したものとして取り扱うこととなります。 | |